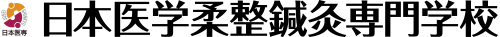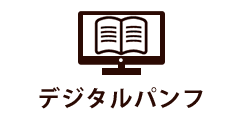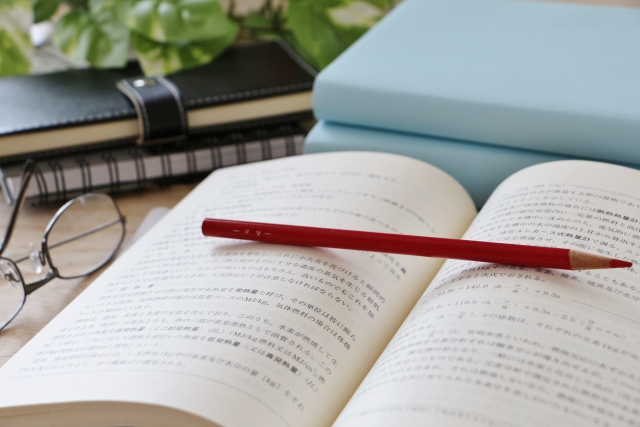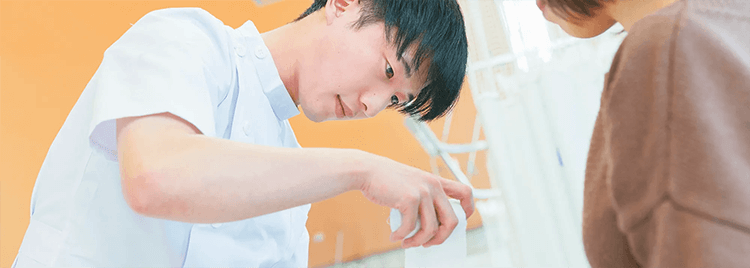鍼灸師について
東洋医学とは?東洋医学と西洋医学の違いなど
東洋医学とは、かつて陸と海のシルクロードでつながっていた地域に伝わる伝統的な治療法のことです。
砂漠や海を渡り、たくさんの陶器、絹織物などといっしょに、医療技術やおくすりが日本にもたらされました。
しかし、具体的にどんな医学なのか、についてはよくわからない方が多いと思います。
鍼灸、あんま、指圧、マッサージ、漢方などが日本では東洋医学とよばれます。
このページでは、そもそも東洋医学とは何か、東洋医学と西洋医学の違い、鍼灸との関係性などについて説明します。

このページの内容

東洋医学とは・特長
現存している古い本に、はりや灸で病気がよくなるという文章があらわれたのが紀元前200から西暦200年頃。西洋はローマ時代、キリスト教が誕生した時期です。それまでにも、薬草を使った治療、現在の漢方薬につながる知識も、アジア各地の地域で気候風土にあわせて、はぐくまれていました。生薬のなかには現在の解熱鎮痛薬の原型になったり、麻酔薬の主成分を利用したものもかつては含まれていたのが有名です。
現在の日本は「老衰」という名の自然死が死因の第3位となり、ケガや感染症で亡くなる人が少なくなっています。お医者さんがつかう薬は感染症などにはとても切れ味が良いのですが、その分、体力の弱った患者さんには効果的過ぎて、使うのが難しいことも。そこで、漢方や、鍼灸、マッサージによって、身体が治ろうとする力を正しい方向に導く治療アプローチが見直されてきています。
東洋医学の主な特長は以下の通りです。
【東洋医学の特長】
・患者さんの治癒力を利用して不調を取り除く
・わるい所だけではなく、全身をみる
・病気を未然に防ぐ
病気やけがの治療だけでなく、病気のキッカケとなった生活習慣などにも注目します。
ホリスティックアプローチ: からだの問題だけでなく、環境や人間関係のストレスまで病気の原因ととらえて、治療法を選択します。
陰陽五行説: ものごとには光があれば、影が生まれます。たくさん運動すれば、体はじょうぶになりますが、やりすぎればケガをします。ほどほどの食事は健康をもたらしますが、すぎれば胃腸の不調がおこります。東洋医学では身の回りの水、火、木などのエレメントがお互いに作用しあう様子を内臓のはたらきになぞらえて考え、不調はそのバランスが崩れているのが原因なので、余ったところはけずり、足りないところへ移動する、といった治療をします。
経絡と気: 経絡は体内を流れるエネルギーの通路であり、気は生命エネルギーです。経絡と気の流れの滞りが健康に影響を与えると考えられます。余った生命エネルギーがあれば、経絡を通じて足りないところへ移動する。ツボをはり、きゅう、マッサージなどで刺激すると気がスムーズに通って、生命エネルギーのバランスが整います。
東洋医学の種類
日本の東洋医学で用いられる治療法の種類として、主に「鍼灸」「あん摩・マッサージ・指圧」「漢方」があります。
・鍼灸
はり(鍼)ときゅう(灸)を用いて経絡と気のバランスを整える治療法です。はりは特定のツボに細い鍼を刺し、きゅうはもぐさ(艾)で温めて治療します。
・あん摩、マッサージ、指圧
経絡や筋肉に手を使ってもむ、おす、さする、軽くたたくなど刺激を与え、血行を良くしたり、気の流れを整えます。
・漢方
植物、動物、鉱物から作られる薬剤を使用して治療を行います。ひとりひとりの症状や体質に合わせて処方されるのが特徴です。
東洋医学の歴史
東洋医学の始まりは、約2,000年前にさかのぼります。
当時はシャーマンが病気を治すと考えられていましたが、次第に経験的医学に発展していきました。
東洋医学が日本に伝わったのは7世紀ごろです。
日本での最古の医学書である『医心方』は、984年に丹波康頼によって編纂されました。
東洋医学は「漢方医学」とも呼ばれますが、これは江戸時代に広まった「蘭方医学」と区別するためのものです。当時の東洋医学は、日本の西洋化の流れもあり衰退していきました。
ところが、明治時代末期に、東洋医学は再評価されます。
日本ではぐくまれた伝統医学として、西洋医学にはない独自性と有用性が見直されたからです。
東洋医学と西洋医学の違い-1 アプローチ
東洋医学と西洋医学は、考え方や治療法が異なります。
昔ほど感染症で人が無くなる時代ではなくなり、労働環境も改善されたため、東洋医学のアプローチは再評価されてきています。近年、漢方、鍼灸、あんま、アロマセラピー、音楽療法などの代替医療を学ぶ時間をカリキュラムに繰り入れるのが、お医者さんの養成課程でも必修とされています。
東洋医学はからだの不調を、生命エネルギーのバランスが乱れてるととらえます。生命エネルギーの流れを調和させるのが治療の目的です。
特徴は、ひとりひとりに合わせたオーダーメイド治療であり、もともとからだにそなわっているエネルギーの調節なので、からだの負担が少ないことです。また、季節によって、同じ症状でもちがうツボを使ったりするなど、環境まで考えて治療法を組みたてます。さらに、ひとりの患者さんに関わる治療時間が西洋医学よりも長めです。患者さんの症状とじっくり取り組み、コミュニケーションをとるので、カウンセリング機能もあります。軽度の認知症患者さんなどは生活の活発化による副次的な効果も期待されています。
西洋医学は病気の原因を目に見える形でとらえて、病名を確定。同じ病名であれば、ほぼ同じ処方薬を与える、標準化された治療手段を用います。もちろん、患者さんの体格や体質によって、薬の量や投薬方法を加減しますが、東洋医学ほど患者さんごとに治療が異なることはありません。また感染症や大けがの治療には右に出るものはありません。
東洋医学と西洋医学の違い-2 診断方法
東洋医学では、脈診、舌診、問診、視診など、全体的な観察に基づいて診断します。患者の生活習慣や精神状態も考慮されます。脈をみるときは、西洋医学と違って、単に脈拍を数えるだけでなく、血管の硬さや左右差などにも細かく注目します。舌をみるときも、舌の場所によって、内臓の不調があらわれるという考え方があり、これも東洋医学独特の観察法といえます。治療をしながらでも刻々と患者さんの生命エネルギーの状態が変化するのに合わせて、治療法を変化させることもあり、治療師と患者さんが協力して治癒を目指すのも西洋医学にない特徴でしょう。
東洋医学では、西洋医学では東洋医学で用いる、患者さんに触れる診察法に加え、血液検査、X線、MRI、CT、生体組織検査など客観的な画像診断に基づいて診断します。薬もそうですが、手術など患者さんの負担が大きい治療を行う分、西洋医学の診断には客観性と厳密性が求められます。
東洋医学と西洋医学の違い-3 治療法
東洋医学は、鍼灸、漢方薬、マッサージ・指圧(推拿;すいな。中国あん摩のこと)、気功、食養生など、からだがもともと持っている治ろうとする力(自然治癒力)を利用していわゆる「ととのえる」治療法が多く使われます。
西洋医学では薬物療法、手術、放射線療法などが使用されます。人口の約3割が65歳以上の高齢者となった現在、日本人がかかる病気の種類が変化し、健康に過ごすための機能訓練や加齢にともなう変化に対応する治療法が西洋医学の現場でも多く用いられるようになりました。
電気を流したり、温めたりする物理療法も再評価されています。
介護保健施設などで、寝たきり状態の患者さんにはよく褥瘡(とこずれ)が発生します。また寝たきりでなくても皮膚が弱って、スキンテア(裂傷)が介助にともない起こります。いずれも皮膚が裂けて、剥がれてしまうのが症状ですが、こうした傷口の治療期間を短縮する効果が期待できるとして、弱い電流を傷口に流す治療が推奨されていたりします。
東洋医学と西洋医学の融合「統合医療」へ
「人生100年時代」となり、健康な時間をできるだけ長く保つことの大切さが本人、家族ともども実感されるようになりました。そして、自分の健康は自分でつくる、自己管理が求められています。それは、病気にならない身体を自ら作るということでもあります。その目的に合っているのが、未病を治す東洋医学であり、鍼灸治療です。体内のバランスを整え病気を治し、病気になりにくい体に「ととのえて」いく。鍼灸治療には、自己管理と未病を治すという相乗効果が期待できるのです。
時代の流れは、「西洋医学のみの医療」へのみなおし時期ともいえるかもしれません。人間の体を総合的に見つめて治療する東洋医学と、現代医療の中心である西洋医学の双方が補い合う医療のあり方がいま注目されています。
看護師が鍼灸師の資格を目指してキャリアアップする、薬剤師のとして製薬会社で勤務していた人が鍼灸師の勉強を始める。このようなキャリアを積んでいく医療人が増えてきています。
東洋医学や鍼灸治療は、いまや世界へと広がっています。鍼灸の教育・研究が世界規模で行われていく中で、2006年にはWHO(世界保健機構)によって経穴部位(ツボの位置)が国際的に標準化されました。また、2018年にWHOが公表した国際疾病分類第11回改訂版(ICD-11)には東洋医学の疾病分類が導入されました。
東洋医学は海外で浸透してきており、いま医療も新しい時代を迎えようとしています。
東洋医学と鍼灸
東洋医学のひとつである鍼灸の歴史は大変長く、約2000年以上の長い歴史があります。
発祥は中国で、紀元前にはすでに体系化された医学が行われていたことを示す本が残っています。
日本に東洋医学がいつ伝わったかはっきりとしたことは分かっていませんが、5世紀以降は東洋医学伝来の記録が残っています。ここから、日本にはおよそ1500年の東洋医学の歴史があるといえます。
その後、安土桃山時代には日本独自の鍼灸が芽生え、江戸時代には技術だけでなく学問的研究も大いに発展しました。はりは鍼医とも呼ばれる専門家が行うことが多い一方で、お灸は灸家などとも呼ばれる専門家のほかに、漢方薬を処方する医家も灸を併用しました。また、一般庶民は昔からお灸を家庭療法として活用してきました。鍼灸は人々の健康を維持・増進する治療法として役立ってきたのです。
その後、明治時代になって政府の方針で西洋医学が強く押し進められると東洋医学の勢いは衰えますが、鍼灸治療は一般からの支持を得続け存続しました。
はりおよび灸を行う免許は明治時代に営業免許として定められ、戦後には現在の「あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律」の原型である法律が制定されて資格免許となりました。
1970年代以降は海外での鍼灸に対する注目が集まり、科学的な研究も盛んに行われるようになりました。近年では東洋医学に対する海外の需要はさらに高まり、鍼灸は多くの国々で行われています。
日本の鍼灸
鍼灸は古代中国ではじまり、のち日本に伝わってきました。中国と日本、それぞれの国で長い年月にわたり受け継がれる中で、道具や治療法は体質や文化に合わせて発展・アレンジされてきたため、中国の鍼と日本の鍼には違いがあります。
一般的に日本では、中国と比べて非常に細いはりが用いられています。
中国では、太いはりを用いることで効果を高めるともされていますが、その代わりに刺激が強いのが特徴です。
細いはりは刺したときの痛みが比較的少ないため、弱い刺激でも体が反応しやすい人が多い日本では普及しました。また繊細な技術を追求する日本では細いはりで様々な症状に対応する技術も発達しました。その中の一つである管鍼法(かんしんほう)は、細いはりと管を組み合わせて用いる技術です。日本で開発された管鍼法は、今では世界中で使用されています。
日本で一般的によく治療に使われるはりは髪の毛程度の細さなので、熟練したはり師であれば刺したときの痛みはほとんどありません。
これまで鍼灸といえば、「頭痛」「腰痛」「肩こり」などの痛みを治療するというイメージがありましたが、近年では痛みの少ない鍼治療を用いて顔に鍼を刺す「美容鍼」が人気となり、小顔効果や美肌に憧れる女性や男性にも話題のはり治療となっています。
「美容鍼灸師」と呼ばれる新たな鍼灸師のジャンルも誕生して、より一層鍼灸師の活躍の場が拡がってきています。
また、痛みをともなわない心地よい鍼灸治療は、自然治癒力を高めたり、健康維持や病気予防のために定期的に受けやすいことも特徴といえます。
【監修者】
本校鍼灸学科 専任教員 稲垣元
鍼灸師