-
 2024/02/02コラム
2024/02/02コラム- 【山中先生コラム】鼻炎(鼻水)対策
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第23弾をお届けします! 鼻炎(鼻水)対策 花粉が飛ぶ季節になりました。 皆さんは、鼻水が出てきたり詰まったりしていませんか? 鼻水問題があると、仕事や遊びに支障をきたす事もあると思います。 そんな時に、是非使って頂きたいポイントをご紹介致します。 ①上星(じょうせい)穴 鼻の延長線上で、髪の生え際から2センチほど頭頂部寄りに入った所にあります。 鼻水を出したい時は、頭頂部から生え際に向かうイメージで上から下へ押す。 鼻水を止めたい時は、生え際から頭頂部方向へ下から上に押す。 ②迎香(げいこう)穴 左右の小鼻の横にあります。 鼻水を止めたい時、くしゃみを止めたい時は少し上方向へぐっと押してみてください。 今、くしゃみ出来ない❗️鼻水をかめない❗️そんな時にも効果的です。 花粉症や、鼻炎でお困りの方は是非使ってみてください。 皆さんの助けになりますよ。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]
-
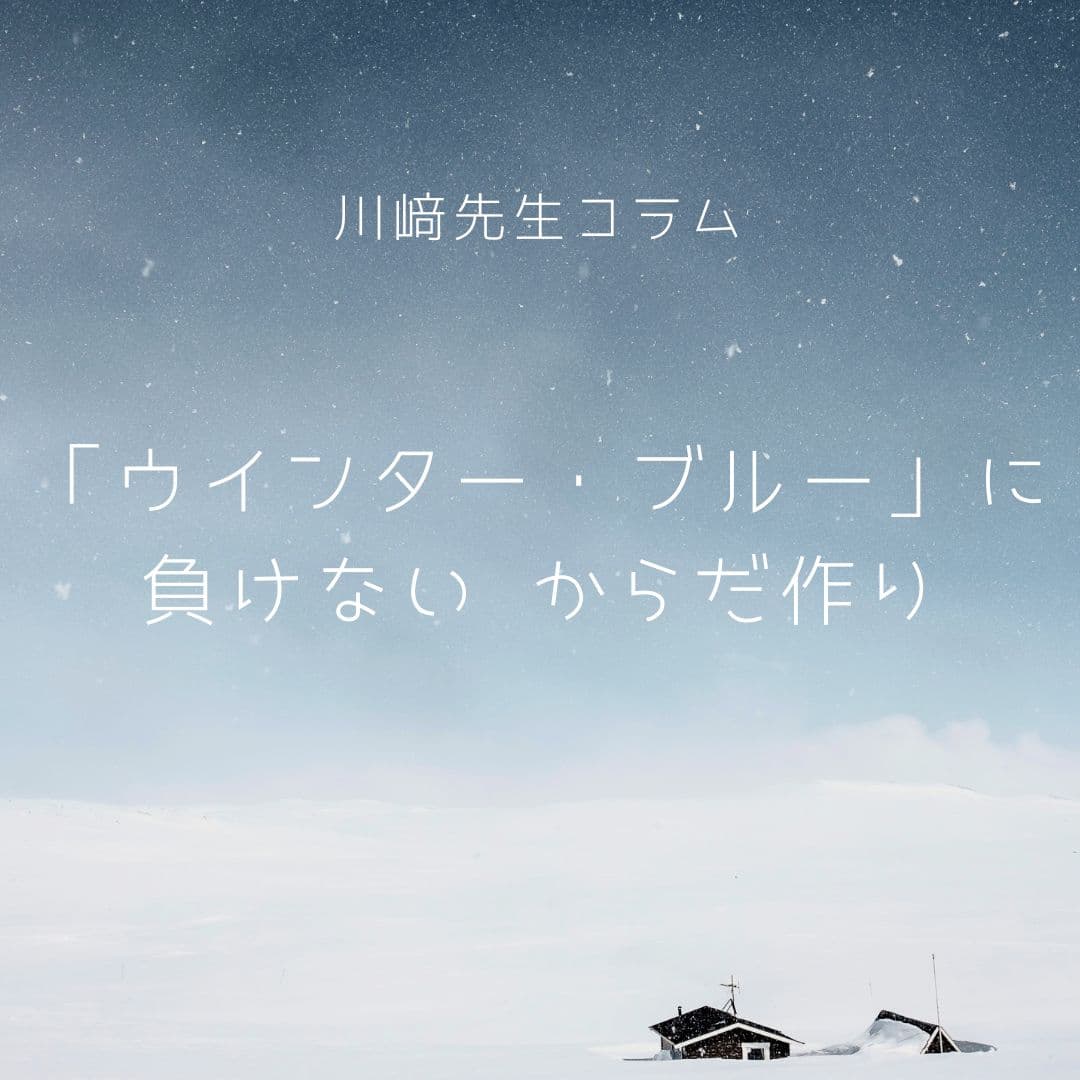 2024/01/26コラム
2024/01/26コラム- 【川﨑先生コラム】「ウインター・ブルー」に負けないからだ作り
-
こんにちは!! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第47弾をお届けいたします! 「ウインター・ブルー」に負けないからだ作り 冷え込みが強くなってきましたね。冬将軍到来ですね。 天気予報で言う「冬日」は最低気温が0度未満、「真冬日」は最高気温が0℃未満で、日本で記録されている最低気温は、北海道旭川市の-41℃(1902年1月25日)だそうです。 この気温は、呼吸をしたら肺が凍ると言われるほどの寒さでとても危険なんです。 冬の季節は日照時間が短く、寒さもあり外出が減っていきますね。 何だか元気が出ないと感じている人も多いのではないでしょうか。 日光を浴びる量が減ると、脳内伝達物質のセロトニンの分泌が減少しイライラしたり気分が落ち込みやすくなって「ウインター・ブルー」(気うつ性感情障害)に陥ってしまいます。 冬になると朝は起きたくない、もっと寝ていたい、炭水化物や甘いものが食べたいなども寒さのせいと思われがちですが、睡眠や食事バランスも日照時間が短いことが影響しています。 ウインター・ブルーになる原因 ウインター・ブルーは、秋~冬にかけて気分が落ち込みやすくなり、気力がなくなり疲労感を強く感じてしまう状態になる「気うつ性感情障害」です。 主な症状は「過食・過眠・体重増加」が特徴です。 特に秋~冬は日照時間が短く、セロトニンという脳内伝達物質の分泌量が減少することが原因です。 セロトニンは脳内の神経伝達物質のひとつで、ストレスを感じると脳から放出されるドーパミン(喜び、快楽など)やノルアドレナリン(恐怖、驚きなど)という神経伝達物質からの情報をコントロールし、心の落ち着きや意欲、感情などを安定させる働きをしメンタル不調を防ぐ役割をしてくれています。 その他、食欲(過剰)や体内時計に働きかけるメラトニンという睡眠ホルモンの分泌が不足するため睡眠にも影響します。 健康な人でも冬はセロトニン分泌量が減りますが、敏感な人は通常の人よりウインター・ブル―に陥りやすくなります。 心身をリラックスさせるさせるためには光を浴びることはとても大切なことです。 春が近づき日照時間が長くなると症状は自然に治りますので、日中は寒くても外出してたくさんお日様を浴びてくださいね。 ウインター・ブルーを防ぐためには ①散歩や運動をしてお日様を浴びる お日様を浴びながら体を動かすことは気分をリラックスさせる効果があり、運動をすると5分後くらいから セロトニン濃度が高まり、20~30分でピークに達します。 疲れを感じるレベルになるとセロトニンの分泌は低下するので頑張りすぎず楽しみながら行うことを勧めます。 ②バランスの良い食事を摂る セロトニンの材料となるのがトリプトファンという必須アミノ酸です。 トリプトファンは動物性タンパク質(肉類、魚、乳製品など)に多く含まれています。 トリプトファンが脳内でセロトニンに変化するには、動物性たんぱく質と一緒にビタミンB6などのビタミン類も摂取することが必要です。 魚や豆類、ナッツ類、バナナ、のりなどを一緒にバランス良く食べることを心がけてください。 一部、糖質(ご飯やパン、甘味類など)を摂ると、インスリンの作用で血中のトリプトファンが脳内へ吸収されやすいとする報告があります。 ③温活で免疫力を上げる 冷えは頭痛や肩こり、肌荒れなど、身体の不調、病気を引き起こす原因のひとつです。 近年では、体温が36℃以下の低体温の人が多くなっています。 低体温では代謝が十分に得られず体のだるさや不調を起こしやすくなります。 体を温めることは大切で、日頃のストレス軽減や疲労を改善することにつながります。 ストレス障害があると免疫力が低下し細胞の中のタンパク質の障害が起こります。 これを修復してくれるのがHSP(ヒートショックプロテイン)と言われるもので、タンパクの障害部位を見つけて細胞を修復し正常なタンパクにして免疫細胞の働きを強化する力を持っています。 HSPは細胞に熱ストレスを加え体温を上げることで増加し、病気やストレスを軽減し治癒に導いてくれる体を守る仕組みの一つです。 だから、入浴による温活で免疫力をアップさせることができます。 効果的な入浴方法は、入浴温度は40~42℃で、10~20分ほど浸かり、入浴後は38℃以上の体温を15分〜20分維持することが好ましいです。 入浴後は体を冷やさず保温することがポイントです。 増加したHSPは、作られてから2日後にその効果を発揮し1週間ほど体内で維持します。 週に2回ほど湯船につかる習慣を作るといいですね。 長く入りすぎたり、入浴温度が43℃を超えると細胞が衰えてしまいますので入浴温度を守って下さい。 最後に 幸せホルモンと言われるセロトニンは、趣味や好きなことをして充実感や達成感を感じるようにすると安定します。 特に、セロトニンは日中に増加し、メラトニンはセロトニンを材料にして夜になると増加する仕組みがあるため、体内時計をコントロールし、規則正しい生活をするように心がけてください。 ウインター・ブルーは誰でも陥る可能性があります。リスクを少しでも減らすようにできることから始めてみましょう。 ♡モノローグ♡ あと1か月ほどで国家試験があります。 3年生は毎日頑張って勉強をしています。 最近、模擬試験や卒業試験で疲れ果てていた学生に癒しの時間を作りモチベーションを保ってもらいたいと思い、ホットストーンセラピー講座を実施しました。 ホットストーンセラピーは、火山岩の一つである玄武岩を使用しオイルトリートメントをする手技で、温まった玄武岩の遠赤外線効果で温めながら体をほぐしていきます。 みんな楽しく積極的に取り組んでくれて、「気持ちよかったー」「癒された―」と元気を取り戻してくれました。 卒業後に仕事に取り入れたいという相談も受け、技術の一つに考えてくれた学生もいました。 あと少しでみんなが卒業してしまうのは寂しい気持ちもありますが、立派な先生になって活躍を期待しています。 日本医専は、卒業後すぐに活躍できる学生を育成することが教育の一つでゼミなど様々な講座を行っています。 自分が教員をしていながら感じていますが、その取り組みは「素敵だなあ~」と学生が羨ましく思います。 1年生も学校に慣れて元気良すぎるくらい楽しく過ごしています。 2月から後期の定期試験が始まるので、放課後残って勉強しています。 お友達と共に教え合い、自己学習力が付いてきていると実感しています。 週に2回の学習会も全員出席していていつもながら集中して取り組んでいます。 1年生は、新しい言葉や知識に戸惑いもありモチベーションが低下しやすいので学習会やJ-UP補講を行って、学習サポートを行っています。 みんなみんな頑張れ!!本当に一生懸命に勉強してますね。 先生たちはその努力をちゃんと見てるから自信を持って下さいね。 だけど、勉強の合間に好きなことをしたり、リラックスする時間も作ってね。 そうするとまた頑張れるからね☆彡 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]
-
 2024/01/19コラム
2024/01/19コラム- 【片橋先生コラム】VRで身体の中を見る
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第47弾をお届けします! VRで身体の中を見る 柔道整復師は人のけがをみる仕事です ですからけがのことをいろいろと勉強しますが、その前に人体をよく知っていなければなりません そのために身体の構造やしくみを学びます 身体の部分の形や名称、どんな働きがあるのかを知っていないと、健康な状態を知っていないとけがをした状態や原因がわからないのですよね だから、身体の構造やしくみはとっても大切 医学の土台になる基礎です じっくりと学びますよ 解剖学 身体の構造を学ぶ科目を解剖学と言います 教科書の文字と図でイメージしながら学んでいきます 人体って立体ですよね 文章や平面の図だけを見ての理解はなかなか難しいです それで、図に加えて模型を使っています 大きさやまわりとの位置関係がよくわかります それでも、細部まですべての模型があるわけではないのですよね・・・ 模型の精巧さもさまざまあります そこでVR!! VRはVirtual Realityの略で、「人工現実感」や「仮想現実」と訳されています 体験したことはありますか? 柔道整復学科専任教員の住吉先生に体験してもらいました! 写真のようなセットで自分で動かして見ることができます 学生さんにお試ししてもらったところ操作はあっという間にできるようになったそうですよ 身体の中に自分が入って自由に動かしながらいろいろな角度から見られるのです 立体映像でああそうなっているのねーと、とてもわかりやすい そして、探求心がくすぐられまくりです! 日本医専はコロナ直後からオンライン授業を開始するなど、新しいものを取り入れてきました VRを取り入れた授業もそう遠くないのかなーー (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]
-
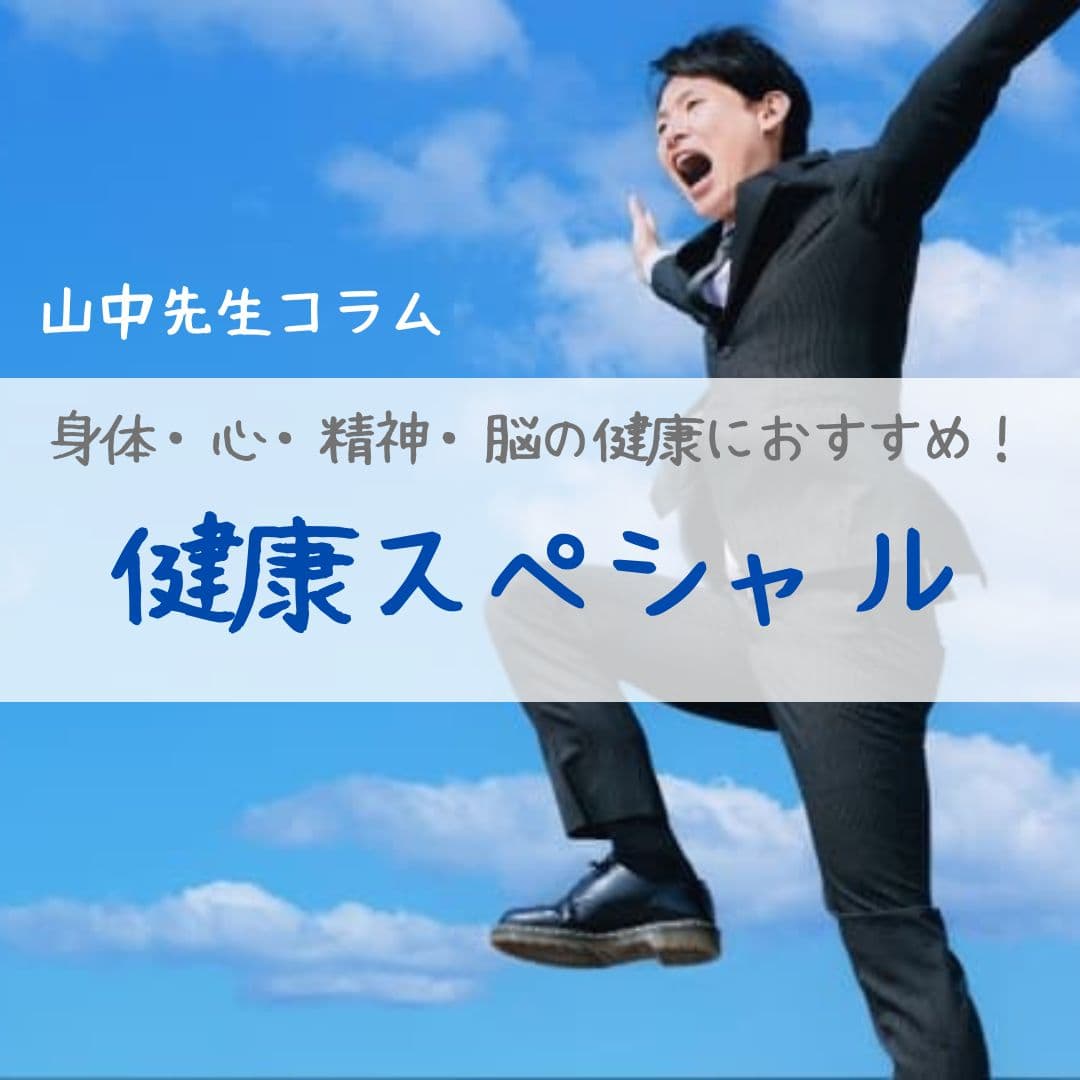 2024/01/12コラム
2024/01/12コラム- 【山中先生コラム】身体・心・精神・脳の健康におすすめ!健康スペシャル
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第22弾をお届けします! 身体・心・精神・脳の健康におすすめ!健康スペシャル 2024年、今年も宜しくお願いいたします。 新年を迎え、皆さんも健康に気を付けながら1年をスタートしていきましょう。 身体の健康、心の健康、精神的な健康、脳の健康等々どれがかけても真の健康とは言えません。 そこで、今年1回目は健康スペシャルとして身体・心・精神・脳の健康におすすめの場所をご紹介いたします。 1.身体の健康 胃腸の疲れや、身体の疲れにオススメ。 足三里(あしさんり) 2.心の健康 心を落ち着けたいときには胸の真ん中の骨を上から下にさすりましょう。 膻中(だんちゅう) 3.精神的な健康 精神を安定させる時につかってみましょう。 内関(ないかん) 4.脳の健康 頭のつかれや、記憶力の助けになりますよ 百会(ひゃくえ) おまけ 身体のだるさがある方は、足の裏にある湧泉(ゆうせん)穴を揉んでください。 正月の疲れや仕事始めで溜まった疲れが取れていきますよ。 ※足の指をぎゅっと曲げたときに出来る足の裏の一番へこむところです。 是非、皆さんの1年のスタートに使用してみてください。 それぞれのポイントを朝起きた時や、夜寝る前などに押してみましょう。 身体・心・精神・脳も健康に1年をサポートしてくれるポイントになると思います。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]
-
 2024/01/11授業見学
2024/01/11授業見学- 【動画あり】柔道整復学科:ホットストーンセラピー
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科 昼間部にてホットストーンセラピーの授業が行われましたので、その様子をお届けします! 担当は柔道整復学科専任教員の川﨑先生です! ホットストーンセラピー ホットストーンセラピーとは、40度~50度に温めた石を使用しトリートメントするオイルトリートメント手技のことです。 筋肉の緊張を緩めていき、体の内側から循環を上げていくことで、副交感神経を高めていきます。 精神的にも安らぎを得ることができるということで、患者さんからの満足度が大きく、治療院でも人気の施術です。 この投稿をInstagramで見る 日本医学柔整鍼灸専門学校(@nihonisen)がシェアした投稿 ホットストーンセラピーの歴史 ストーンセラピーは、2000年もの前から使用されてきたことが記録に残っており、様々な地域で療法に使用されてきました。 植物療法と同じく、身近にあるものを利用した自然療法の一つです。 柔道整復師の自費診療のなかのマッサージにも含まれる【補完代替医療】や【ホリスティック医学】で活用されています。 西洋医学のなかの「病気を治す」ということは出来ませんが、「病気を治すために人間の自然治癒力を高めていく治療」ということが、柔道整復師は可能です。 心と体、魂といった、本質のところへアプローチをかけていき、西洋医学の考え方を活かしています。 中国医学やインド医学など各国の伝統医学のなかでも心理療法で使われたり、栄養療法、手技療法、運動療法などを補完し合うような代替療法を総合的に使用し、自然治癒力を高めていくことが歴史の背景にあります。 リラクゼーションではありますが、治療という目線で見ることもできるのです。 ホットストーンセラピーの効果 ホットストーンの温度は筋肉の表面から深さ1.5インチの箇所にまで到達するといわれていて、熱が行き渡ることで代謝を高めて老廃物の排出を促します。 その効果はハンドトリートメントのみの場合より3~5倍ほどの高い効果があるのです。 また、自然のエネルギーを持つといわれるホットストーンのパワーで、心と体のエネルギーバランスを整えるヒーリング効果や、エッセンシャルオイルの香りがもたらすリラクゼーション効果も期待できます。 ■主な効果 むくみ、冷え性、生理不順、肩こり、腰痛、頭痛、不眠症、心身のリラックス ホットストーンセラピーは即効性が期待できる反面、好転反応(疲労感・のぼせ・発熱など)が通常のトリートメント手技よりも強く出る場合がある為、注意が必要です。 施術者としての禁忌・注意事項をしっかり学び、実際に施術していきます! ふくらはぎのストローク まずは置き石といって、指の間に石を挟んでいきます。 そして、ふくらはぎの部分を円を描くようにオイルマッサージを行い、この手の使い方を利用しながら、石を使用してマッサージしていきます。 手の使い方、圧のかけ方、タオルマナーなど、患者さんにリラックスしていただくために、ホスピタリティの部分も学んでいきます。 エステに勤務されている方や、柔道整復学科の人気のゼミであるボディメイクゼミを受講されている方々は、慣れた手つきでしたね♪ <<ボディメイクゼミについてはこちら>> 学生同士で交互に施術していき、施術が終わると「足が宙に浮いたような気分」「足が温かくなった」と効果を実感する声があがりました。 \左右で見比べてみると、かかとの色味の違いが一目瞭然です✨/ 日本医専ではこのように、リラクゼーションやボディメイクなど、時代のニーズに合わせた施術を学ぶことができます。 オープンキャンパスでもこちらのホットストーンセラピーを体験できますので、是非お越しください! 皆様のご来校、心よりお待ちしております! <<お申し込みはこちら>>]
-
 2024/01/05ゼミ活動
2024/01/05ゼミ活動- 【トレーナーゼミ】他のパーソナルトレーナーとの差別化!柔道整復師だからこそできる技
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 3つのゼミで手技を磨く【未来活躍プログラム】のひとつ、「トレーナーゼミ」の取材へ行ってきました! 【未来活躍プログラムとは?】 トレーナーゼミ、ケガゼミ、ボディメイクゼミの3分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 トレーナーゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際に必要とされる知識や技術を学びます。 講師は、日本医専トレーナーズチーム(NITT)トレーナー講師陣の一人で、オリンピック選手の指導経験もある土黒秀則 先生です! ・JHCA-FC・NSCA-CSCS ・NSCA-認定検定員 ・早稲田大学スポーツ科学部非常勤講師 [ トレーナー実績 ] ・JISSトレーニング指導員 ・ロンドンオリンピック<競泳>松田丈志トレーニングスタッフ ・05‘世界水泳シンクロトレーニングコーチ ・セパタクロー女子日本代表選手トレーニング指導 ・早稲田大学スキー部トレーニング指導 普段は「ケガの処置」を学ぶ柔道整復学科の学生たち。 ケガをした後ではなく、ケガの予防とコンディショニング、ケガをさせない技術を学べるということで、当日は多くの学生が参加! 本校は現役パーソナルトレーナーの学生も多く、授業前から土黒先生に質問する姿が印象的でした。 前回、コンディショニングと、患者様ご自身で行っていただくセルフコンディショニングの方法を学びました。 <<前回の授業の様子はこちら>> 今回はより実践的な手技と呼吸法を学んでいきます。 スポーツ現場やトレーニングの現場で、「ストレッチを左右それぞれ1分間、左やったら右」などと均等にやりがちですが、体は左右非対称で左右差があります。 まずはその左右差を評価し、左右それぞれのアプローチ方法を丁寧に説明。 現場で実践できるよう、土黒先生が学生1人1人を細かくチェックしていきます。 ビフォーアフター 評価前とアプローチ後の違いを比べてみました! 見た目で一目瞭然ですね! 「コンディショニングで、良い状態に仕上げる。 健康であったとしても、もっと良いレベルにもっていくことができる。」 その土黒先生の教えを、身をもって体感できました。 「国家医療資格を持つ者だからこそ行える、体を理解した施術」を、皆さん吸収していきます。 授業では学べない、コンディショニングとセルフコンディショニングのやり方を教わったので、現役パーソナルトレーナーの学生からは「早速実践してみます!」との声。 「ケガの予防」に繋がる、第一線のコンディショニングの技術をこのトレーナーゼミで学び、他のパーソナルトレーナーとの差別化を目指しましょう! お疲れ様でした!]
-
 2023/12/22コラム
2023/12/22コラム- 【川﨑先生コラム】動的ストレッチで年末年始を健康に過ごそう💛
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第46弾をお届けいたします! 動的ストレッチで年末年始を健康に過ごそう💛 皆さん、お元気にお過ごしでしょうか。本当に1年が経つのは早くて今年もあとわずかですね。 今年も年末のご挨拶をさせていただく時期を迎えました。 この1年、コラムを通じて皆様の健康をサポートしてまいりましたがお役に立てたでしょうか。 お読みになってくださりありがとうございます。本当に感謝申し上げます。 さて、年末年始といえば、クリスマス、忘年会、お正月、新年会などイベントがたくさんあり、お食事会やお正月の伝統料理など、美味しいお料理をたくさん食べてしまいますね。 そして、忙しい日々から解放されてゆっくり過ごすことで運動不足になりがちです。 多くの人が気にすることは、体重が増えた、脂肪がついた、体がだるく重い、疲れやすくなったなど、お正月明けの身体の状態です。 最近では、「お正月病」と言われていて、食生活の変化、夜更かし、運動不足が原因で生活リズムや睡眠リズムが崩れて「心」と「体」に異変が生じてしまいます。 そうなることにより、いつも疲労感を感じ、やる気が湧かず新年から前向きに過ごせなくなってしまいます。 予防対策として、今回は動的ストレッチについてお話をしていきたいと思います。 1.ストレッチの効果 ストレッチには、柔軟性の向上、疲労回復、血行促進、リラクゼーションなどの効果があります。 柔軟性を向上させることで筋肉の緊張が緩和され、動きやすい体になります。 また、筋肉を伸ばして緩めることで血行が良くなり代謝がアップするので、疲労回復や脂肪の蓄積予防につながります。 幸せホルモンであるセロトニンの分泌も促進されるので、自律神経の乱れや精神的なバランスもコントロールすることができます。 2.ストレッチの方法 ストレッチには、「静的ストレッチ」と「動的ストレッチ」があります。 今回は、主に動的ストレッチを実施してほしいですが、動的ストレッチの後に、静的ストレッチを行うと更に効果的です。 1日10分程度の時間で十分ですので自分のペースでやってみてください。 ①静的ストレッチとは 主に、運動後のクールダウンに行われるストレッチで、目的とする筋肉を伸長しその状態で数秒~数十秒間姿勢を保持していきます。 いわゆる柔軟体操です。 筋肉の緊張を和らげ柔軟性を高め、副交感神経を優位にする効果があります。 リラックス効果が高く疲労回復を早めてくれます。 ②動的ストレッチとは リズミカルに体を大きく動かし筋肉の伸縮を繰り返すストレッチです。 筋肉を活動的に動かすことで、交感神経が優位になり、身体の代謝活動が高まり体温が上昇します。 それにより、筋肉の柔軟性と関節の可動性を高める効果があります。 身近な運動でいえばラジオ体操が動的ストレッチになります。 食べすぎ、ダイエット、冷え、むくみ、肩凝り、腰痛には動的ストレッチがおすすめです。 運動習慣がない方や日常の疲労で筋肉が硬くなっている人は、関節を動かしずらく動的ストレッチが負担になってしまうことがありますので、その場合は、静的ストレッチを最初に軽く行いほぐしてから動的ストレッチを行ってください。 3.スロートレーニング 軽い負荷(自分の体重)をかけた状態でゆっくり筋肉を動かすトレーニングです。 筋を緩めずにトレーニングをすることで、低強度の負荷でも高強度の負荷と同じ効果が得られ、筋力増強効果が高いとされています。 インナーマッスルを鍛え、基礎代謝を向上させる効果があるため、長期間のダイエットにおすすめです。 関節をロックせずに、5秒かけて動いて、5秒かけて戻る動きを30秒~1分繰り返します。 毎日行うのではなく、週に2~3回のペースで、長期間行うことが理想的です。 短期間では効果がでません。 簡単な運動には、スクワット、膝の伸展、腕立て、腹筋、カーフレイズなどの運動があります。 4.運動の後のリラクゼーション法 リラクセーション法は、リラックス反応を誘導しストレス反応を低減させることで、心身の回復機能を向上させる方法です。 心身の自律機能が回復し、ストレス反応が起きにくい体へと変化させることが目的で行います。 自己コントロールが難しいという時は、運動よりもリラクゼーションを重視して取り組んでみてください。 ①漸進的筋弛緩法 筋肉の緊張と弛緩を繰り返し行うことにより身体のリラックスを導く方法です。 方法は、身体の特定の筋肉に意識を向けながら、意図的に強く緊張をさせその後一気に力を抜いて脱力していきます。 おおよそ、各部位の筋肉に対し、10秒間力を入れて緊張させ、15~20秒間脱力・弛緩します。 ②呼吸法 腹式呼吸によって自律神経に働きかけ心身をリラックスさせる方法です。 ストレスにより緊張状態では、呼吸は浅くて速い呼吸になります。 その反対に、リラックス状態では、深くてゆったりとした呼吸になります。 緊張しているときに、深くゆったりした呼吸をすると副交感神経の働きを促進し、気持ちが落ち着き心身の活動を高めることができます。 終わりに 年末年始は、普段の生活スタイルを維持するのが難しいですね。 家族や親戚、友達が集まり、楽しくリラックスして過ごせる機会が増える反面、食事に偏りが出たり、運動不足になり、また余分なストレスを溜めてしまうこともあります。 1年のスタートをスッキリした気持ちで迎えられるように健康的な過ごし方を意識してみてください。 2024年は辰年ですね。 辰年でも甲辰(きのえたつ)にあたり、草木の芽生えや大きく育った樹木といった「成長」を感じさせる意味がある年です。 私自身、成長できるように来年も色んなことにチャレンジしていきたいと思います。 皆様、年の瀬を迎え気ぜわしい毎日かと思いますが、どうぞお健やかに良いお年をお迎えください。 ♡モノローグ♡ 最近、編み物をしています。かぎ針編みが好きなのでYouTube動画を先生にして色々チャレンジしています。 編み物には、マインドフルネス(目の前にあることだけに集中すること)による癒しの効果があり、「ニットセラピー」と言われる精神安定療法や作業療法でも使われています。日本では趣味として捉えられていますが、欧米や欧州ではセラピーの一つとして確立されているんです。 無心で編み物をしている時は、余計なことを考えずに編み目に集中しているので「自動思考」が浮かびにくい状態になります。 それは、瞑想に近い状態になっていて、瞑想はストレスを解消する効果があると考えられています。 だから、編み物は、瞑想のようなリラックス状態を作り出すことができるんです。 編み物の効果は、脳を活性化することができ集中力を高めることができます。 また、リラックスや癒しの効果にによって、ストレス解消に繋がり質の良い睡眠にもつながります。 私自身、編み物をしていると間食も減ったのでダイエットにも向いているかもしれませんね。 編み終わった後の達成感と嬉しい感情が湧き、編んだものをずっと眺めてしまいます。 仕事に追われる生活でも、自分の趣味を楽しむ時間を作ることの大切さをとても感じています。 最近、編んだものです。 ・クマさんのポーチ ・ミニショルダーバック ・ハンドウォーマー ・座布団 今は、ニット帽とショールにチャレンジしています。 全部、100円ショップで購入しています。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子]
-
 2023/12/14コラム
2023/12/14コラム- 【片橋先生コラム】アキレス腱
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は柔道整復学科専任教員 片橋先生によるコラムの第46弾をお届けします! アキレス腱 今日はアキレス腱の話です みなさん、アキレス腱はご存知だと思います 踵のアレ、太いスジですね 以前のコラムで筋肉は腱になって骨についていると書きました アキレス腱の筋肉はどれでどの骨についているでしょうか? 正解は・・・ふくらはぎの筋肉から踵の骨まで! ふくらはぎの筋肉は二重構造です 表面を腓腹筋(ひふくきん)、奥をヒラメ筋といいます これらの筋の腱があの太いアキレス腱で、踵の骨、踵骨(しょうこつ)についています 踵の骨も大きいんですよ この太いアキレス腱が切れるって聞いたことはありますか? 意外と多いんですよね 特に運動会シーズンでしょうか この腱を切ってしまうのは運動会の主役のお子さんではありません そう、付き添いのお父さんお母さんなんですよね どうしてでしょう? 実は、ケガにも年齢が関係しています 年を取ってくると腱の柔軟性、弾力性が少なくなっていくのです そんなときに、急激な運動をしてしまうとあんなに太いのに腱は切れてしまうんですよね アキレス腱を切った方はみなさんその衝撃を実感していらっしゃいます ばちーんとすごい音がした、だれかに蹴られたと思った、などとおっしゃいます それだけ太い腱が一瞬で切れてしまうのですね 予防としては、アキレス腱を伸ばす、身体を温めるようにウォーミングアップをする、長時間運動しない、無理なことをしないがあげられます もちろん、絶対切れないということではありませんが、予防するのは大切なことです (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]
-
 2023/12/13ゼミ活動
2023/12/13ゼミ活動- 【トレーナーゼミ】コンディショニングのプロから「ケガをさせない技術」を学ぶ!
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 3つのゼミで手技を磨く【未来活躍プログラム】のひとつ、「トレーナーゼミ」の取材へ行ってきました! 【未来活躍プログラムとは?】 トレーナーゼミ、ケガゼミ、ボディメイクゼミの3分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 トレーナーゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際に必要とされる知識や技術を学びます。 講師は、日本医専トレーナーズチーム(NITT)トレーナー講師陣の一人で、オリンピック選手の指導経験もある土黒秀則 先生です! ・JHCA-FC・NSCA-CSCS ・NSCA-認定検定員 ・早稲田大学スポーツ科学部非常勤講師 [ トレーナー実績 ] ・JISSトレーニング指導員 ・ロンドンオリンピック<競泳>松田丈志トレーニングスタッフ ・05‘世界水泳シンクロトレーニングコーチ ・セパタクロー女子日本代表選手トレーニング指導 ・早稲田大学スキー部トレーニング指導 普段は「ケガの処置」を学ぶ柔道整復学科の学生たち。 ケガをした後ではなく、ケガの予防とコンディショニング、ケガをさせない技術を学べるということで、当日は多くの学生が参加しました。 コンディションとは、体力や技術の「身体的要因」と気温や用具などの「環境的要因」、そして「心因的要因」をいいます。 選手の要望や患者さんの目的を達成するためには、このコンディションを望ましい状況に整えることが必須です。 一瞬で力は強くなるのか? 少しアグレッシブな写真ですが笑、パフォーマンスの力を強める方法と、逆に弱めてしまう要因を教えていただきます。 自分の意志に反して力の強弱が変わることを体験し、教室中から驚きの声があがりました。 こういった強弱をコントロールできる知識も、トレーナーとして大切なことですね。 土黒先生の笑いを交えた説明により、楽しい雰囲気で授業が進んでいきます。 日本医専の実技授業は教員2名体制で行います。 専任教員の大隅先生も学生をしっかりサポート! 歪みの矯正 時間いっぱい、歪みの矯正に向けた様々な手技を教えていただきます。 コンディショニングと、患者様ご自身で行っていただくセルフコンディショニングの方法も教わり、より実践的な手技を学ぶことができました。 土黒先生は次回、より実技に重点を置いた授業をしていただきます。 授業が終わっても熱心に土黒先生へ質問をする学生の姿が印象的でした。 「ケガの処置」だけでなく「ケガの予防」もできる、第一線のコンディショニングの技術を土黒先生から次回もしっかり学びましょう! お疲れ様でした!]
-
 2023/12/10コラム
2023/12/10コラム- 山中先生コラム~食欲不振~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校です。 柔道整復学科専任教員、山中先生によるコラム 第21弾をお届けします! 食欲不振 みなさん、疲れや気温差で胃腸に疲れが出てきていませんか? お腹が空かない、食事を前にすると食べられない。 食べられても少量でお腹がいっぱいになってしまう。など、ないでしょうか? そんな時にオススメのポイントを、2つご紹介します。 是非、食前にためしてみてください! ①足三里(あしさんり) スネ(脛骨)の外側、膝のお皿から指4本ほど下にあります。 ②中脘(ちゅうかん) へそと溝落ちの真ん中にあります。 この2つが、冷えている場合は温める。硬い場合は解きほぐすようにしてみてください。 皆さんの日々の助けになると思います! 是非試してみて下さい。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 ▽山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ 是非ご覧ください!▽]
- お問い合わせ
- info@nihonisen.ac.jp
- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30
- LINEで問い合わせる







