-
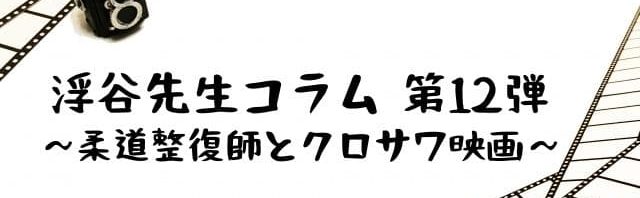 2021/10/15コラム
2021/10/15コラム- 浮谷先生コラム 第12弾~柔道整復師とクロサワ映画~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 浮谷先生コラムの第12弾をお届けいたします! ~柔道整復師とクロサワ映画~ こんにちは。柔道整復学科専任教員の浮谷です。 これまで自身のコラムでオリンピックの話題と共に映画監督・小津安二郎さんについて記してきました。 本日は小津監督と並ぶ世界のクロサワ‼~黒澤明監督について、特に柔道関連の作品を探っていきたいと思います。 では初めに皆さんがどのくらい黒澤作品を知っているか? 国試型式で出題します。 是非チャレンジしてください! 問1. 以下の映画の中で黒澤明監督が手がけた最初の監督作品はどれか。 1. 生きる 2. 七人の侍 3. 姿三四郎 4. 用心棒 【解答・解説】 答えは3.選択肢はいずれも黒澤監督の名作ですが、「姿三四郎」がデビュー作です。 時は昭和18年、太平洋戦争の真っ只中です。 この作品は富田常雄氏の同名小説の映画化でした。 主役の三四郎を演じたのは藤田進。 彼は「ハワイ・マレー沖海戦」や「加藤隼戦闘隊」といった当時の戦意高揚映画に出演したスター俳優でした。 作品は明治中期、古くからの闘技としての柔術と、講道館設立の父・嘉納治五郎による近代スポーツとしての柔道との対立が激しかった頃が題材として取り上げられています。 この作品は好評だったため、やがて続編が作られました。 問2. 前作の続編のタイトルで正しいものはどれか。 1. 柔道一直線 2. 続姿三四郎 3. 新姿三四郎 4. 帰ってきた三四郎 【解答・解説】 答えは2.続編のためそのまま「続―」としたのか?時局柄(昭和20年、封切りは終戦直前の5月)適当なネーミングを探す余裕がなかったのかもしれません。 内容は前作とほぼ同様、藤田進主演です。 ただ戦時色が前作よりさらに濃くなって、例えば乱暴なアメリカ人船員を三四郎が投げ飛ばしたり、外人ボクサーと柔術師との試合のシーンがあったりして民族意識を高める傾向が見られます。 おそらく当時の軍部の意向と思われますが、「三四郎」「続三四郎」2作品ともに決して黒澤監督は戦意高揚を狙って作ったわけではないと多くの識者が述べています。 あの時代、軍部の統制下にあって明治の柔術~柔道を題材に質の高い娯楽・芸術作品を撮り、その後の『世界のクロサワ』の基盤となった記念すべき作品と言えるでしょう。 柔道整復師を目指す皆さんには柔道の歴史を知る手がかりになると思います。 これらの作品は小津作品同様、現在上映の機会は少ないですが、DVDがありますので是非ご覧ください。 最後に:『日本医専の姿三四郎』といえば、どなたでしょう? ⇒やはり柔道整復学科で本校柔道部出身の熱血漢‼森下先生しかいませんね。 失礼いたしました。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら]
-
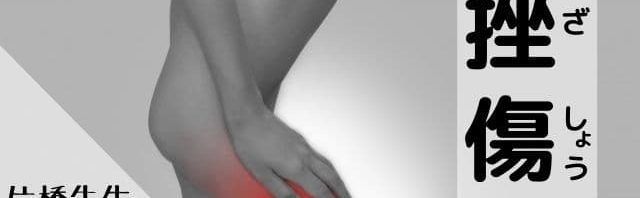 2021/10/08コラム
2021/10/08コラム- 【片橋先生コラム・第13弾】~挫傷~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第13弾! 挫傷 みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 お元気でお過ごしでしょうか。 やっと緊急事態宣言が解除されましたね。 まだまだ安心はできませんが、気持ちは少し楽になりますね。 心の緩みが感染対策のゆるみにならないよう、自分の身を守りながら生活していきたいです。 「挫傷」は読めましたか? 「ざしょう」と読み、柔道整復師の仕事(業務範囲)です。 身体表面には創(そう、きず)がなく、内部の軟部組織が損傷された状態に「傷(しょう、きず)」を使います。具体的には挫傷は肉ばなれのことを指します。 肉ばなれというと経験がある方もいらっしゃると思います。 スポーツをしている最中に起こることが多いです。 走ったり蹴ったりの動作で発生しやすいため、特に下肢に起こります。 具体的には太ももの前後の筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングス)やふくらはぎの筋肉(腓腹筋)です。 筋肉は筋線維と呼ばれる細長い構造をしていて、左右の指同士を重ねたり離したりするようにして収縮(力を入れる)と弛緩(ゆるむ)をしています。 筋肉が収縮している時に、その筋肉にを強制的に引き延ばされる力がかかって筋線維が部分的に断裂するのが肉ばなれです。 踏ん張っているときがこの状態になっています。 疲労によって筋肉がスムーズに動かせない、寒冷、筋肉が硬い、反対の作用をする筋同士のバランスが悪いなどが原因です。 肉ばなれが起こると損傷したところが痛みます。 傷の程度によりますが、優しく触ると痛みとともにポコッと少し凹んでいるのを感じることがあります。 このへこみ(陥凹)があって、起きた原因が前述のような動作であると肉ばなれの可能性が高いです。 行っていた運動を止めてRICE処置をします。 RICE処置はケガの処置の基本です。 R: rest 安静 I : icing 冷却 C: compression 圧迫 E: elevation 挙上 これらは損傷部の腫れや出血、痛みを抑えるためにします。 ケガをした足が少し高くなるような姿勢をとって横になり、15分程度冷やします。 RICE処置ができなければ、そのまま接骨院やクリニックへ行きましょう。 安静と固定が治療の中心になります。 肉ばなれは筋肉に傷ができた状態ですので、傷口が寄るように、筋肉が少し緩むように固定します。 肉ばなれは繰り返しやすいのですが、原因の1つに傷口・傷跡の大きさがあります。 治っても傷跡は弱い部分ですのでそこが大きいと切れやすいのです。 また、再発防止のために運動前にストレッチをして筋肉をやわらかくしておくことや、ウォーミングアップをして体を温めるなどの準備、疲れをためないで体調を整えておくことが大切です。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]
-
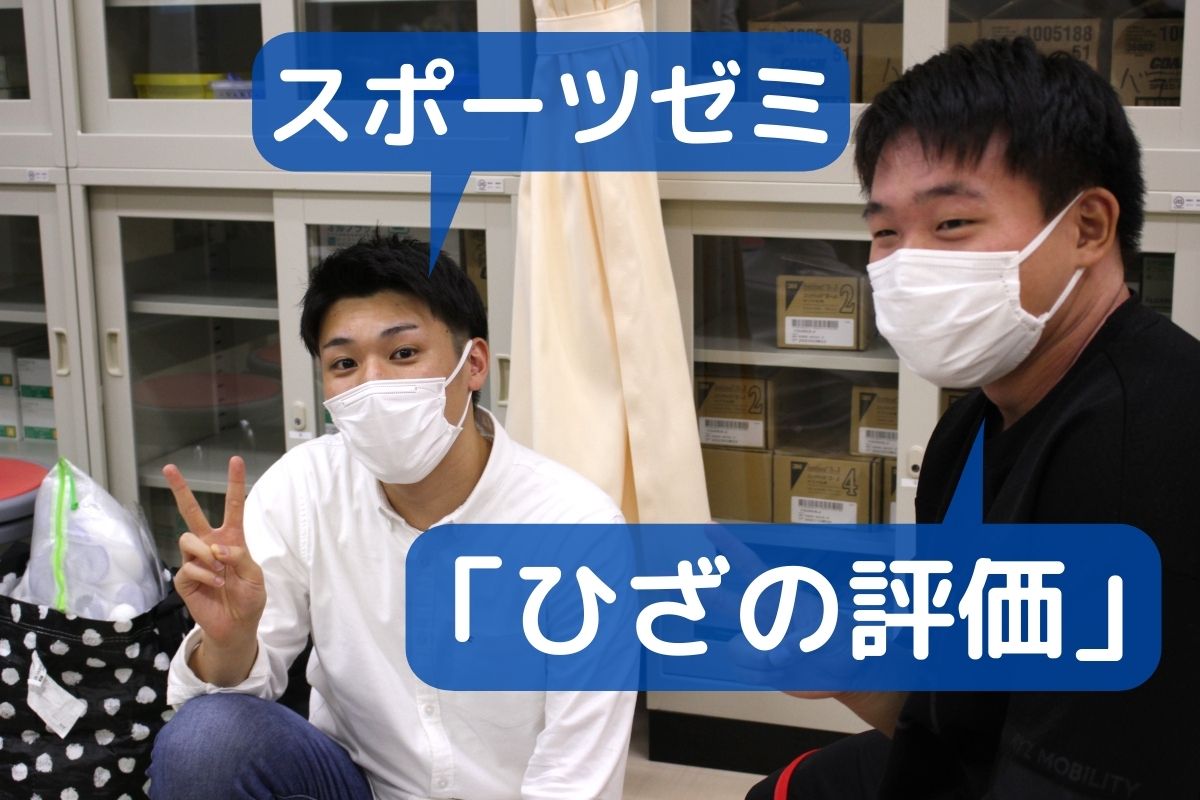 2021/10/06ゼミ活動
2021/10/06ゼミ活動- 【スポーツゼミ】ひざの評価
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日です。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 今回は三田先生の講義の様子を取材しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 ひざの評価 前回の三田先生の講義では肩の検査法と施術を学びましたが、今回はひざの検査法を学びました。 スポーツ現場ではひざに負担がかかり、ひざやその周辺に障害・外傷が起きる場面が多いです。まずは三田先生が実際に受け持った患者さんを例に出してカルテを書いていきます。 次にオスグットやジャンパー膝、前十字靭帯損傷など、ひざの障害・外傷で多い症例を三田先生が詳しく解説していきます。 学生のみなさんは知っている障害・外傷の名前もあり、三田先生の説明を真剣に聞いてしっかりとメモを取っていました!たまに面白いエピソードも交えつつ説明するので、笑顔がこぼれる場面も♪ 最後に残った時間で三田先生が良く行っているひざ周囲のマッサージを披露!マッサージをすることで筋肉の緊張をほぐしケガをしにくい体を作ることができるとのこと。 次回のスポーツゼミでは実際にひざのマッサージを練習します!! 本校ではゼミの見学会も行っています。 >>ゼミ見学会のお申込みはこちら 是非お気軽にご参加ください。 みなさまのご来校を心よりお待ちしております! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
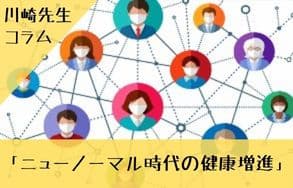 2021/10/01コラム
2021/10/01コラム- 川崎先生コラム 第12弾「ニューノーマル時代の健康増進」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川崎先生コラムの第12弾をお届けいたします! ニューノーマル時代の健康増進 コロナ渦以降、社会のほとんどがニューノーマル時代を迎え生活様式や働き方が一変しました。 ニューノーマルとは、時代の転換期、新しい常識・常態という意味があります。 今まではビジネスで使用される言葉でしたが、コロナ渦で世界中が以前の常識が通用しない生活様式となり通常に使用されるようになりました。 その代表としてはリモートワーク中心の働き方改革。 生活ではステイホーム時代になりインターネットショッピングや宅配の利用が増加したことが代表的です。 しかし、急速に普及したニューノーマルな生活や働き方は、健康にも大きく変化をもたらしています。 【ニューノーマル時代の健康のリスク】 ①疲労を感じやすくなる 今まで通勤や外出によって歩く時間が普段の活動で得られていましたが、巣ごもり生活で体を十分に動かさないことによる身体機能の低下、心肺機能の低下、体力の減退、筋力の低下などが疲労を感じやすくなる原因となります。 生活の質も低下するため適度な運動を心がけるようにしましょう。 ②疾病の罹患リスクが上昇 エネルギー消費量が減少したことで、太りやすくなったと感じる人も多いのではないでしょうか。 運動不足は疾病の罹患リスクが上昇します。 活動量の低下や1日中座っている時間が多くなると、腰痛や肩こりの原因となり、肥満、高血圧、脂質異常などの生活習慣病のリスクも高まります。 また、長時間座っている時間が長いほど心筋梗塞・脳卒中・癌で死亡するリスクが増大すると言われています。 エネルギー消費量が多いほど疾病の罹患や死亡リスクは低下します。 1時間に1回程度、仕事の合間に体を動かす意識を持つようにしましょう。 ③メンタルヘルス不調 メンタルヘルス不調は、異常に対する正常な生体反応です。 ニューノーマル時代に対応できず不安や焦りを感じたり、社会生活に適応できず精神的ストレスが大きくなり身体の不調を抱えている人も多いのではないでしょうか。 特に、人と会う機会が少なくなり、親しい人と何気ない会話で和んだり、コミュニケーションを取ることができないことでモチベーションの低下や精神的疲労も生じます。 外出制限も好きな活動ができない精神的ストレスになります。 コロナ鬱という言葉を時々聞くことがありますが、気分の落ち込みにより何事も手につかないことが問題となっています。 人は五感から脳へ情報を送り無意識で心身活動に影響を働きかけます。 脳は全身をコントロールしているため、考え込むほど様々な病気を引き起こしてしまいます。 可能な範囲で外出し人と話す機会を作ったり、日常の生活の変化をつけるなど、部屋の模様替えや体を動かす作業をしてみるのも気分転換となります。 メンタルヘルス予防を心がけましょう。 リモートワークや巣ごもり生活が続くことで意識的に運動をしたり、新しい趣味にチャレンジする方も多いと思います。 こうした自分時間を大切にして生活のメリハリをつけるようにしていきましょう。 意外と時間があると思って1日のスケジュールがはっきりしない生活をしていると仕事を終わらせる時間が遅くなり深夜まで作業をしてしまうケースが多く見られます。 結果的に労働過多となり睡眠障害なども起こる可能性があります。 生活習慣を一定リズムに保つことを心がけていきましょう。 残暑厳しいですが少しずつ涼しくなり過ごしやすくなってきました。 この時期は、夏の疲れや気温の変化による体調不良が起きやすい時期です。 特に女性は運動不足や筋力低下は冷えの原因となります。 少しずつ体を動かして冬に備えていきましょう。 そろそろ、お肌の乾燥が気になる季節になりますね。 乾燥にはナツメがいいそうです。 世界3大美女の楊貴妃も食していたナツメは1日3個食べれば歳をとっても老いが現れないというほどの健康と美容に関する効能があります。 その他、疲労回復、腸内環境を整え、冷えや代謝亢進、貧血、精神安定作用などがあります。 私は、冬になると鍋料理に入れて食べます。 ほんのり甘くておいしいです。 ナツメ茶もおすすめです。 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 柔道整復師・鍼灸師 川﨑先生はオープンキャンパスも担当しておりますので、興味のある方はぜひご参加ください。 >>日本医専のイベント情報はこちら 授業、ゼミの様子やコラムが盛りだくさん! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
 2021/09/28ゼミ活動
2021/09/28ゼミ活動- 【ヘルスケアゼミ】腰やひざの痛みにおける運動療法の必要性
-
みなさんこんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校、広報担当です。 本校 柔道整復学科の魅力のひとつ、4大柔整ゼミの中の『ヘルスケアゼミ』が行われました! 【4大柔整ゼミ】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ケアゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 <<詳しくはこちら>> 今回のヘルスケアゼミでは、トータルフィットネスクラブ・株式会社 わらわらの最高技術責任者 板井さんが教えてくださいました! 今回のテーマは「腰やひざの痛みにおける運動療法の必要性」です。 授業では腰やひざの痛みに対して、外科的治療や物理療法などで患部に直接的にアプローチする方法を学びますが、今回板井さんには、そもそもケガをしない、これ以上患部を悪化・再発させないようにする「運動療法」でのアプローチ方法を学びました! まずは外傷・障害へ外科的治療や物理療法などで直接的なアプローチを復習です。 そのうえで物理療法などでアプローチしたとしても外傷・障害の再発の可能性は制御できないと説明があり、再発防止や悪化させないために運動療法の必要性を教えてくださいました! 次は腰とひざに痛みがあるときに、筋や骨格がどうなっているのか、こんな症状のリスクがあるのかを解説! そして、運動療法を行う前にする体のチェック方法やオープンブックストレッチ、プレイヤーストレッチなどの運動療法を実際に体を動かしながら勉強しました。 実際にやってみるとなかなかハードな運動療法で、やった後にはみなさんヘトヘトになっていました! ヘルスケアゼミ担任の西村先生にもモデルになってもらいました!! 今回のゼミで運動療法でのアプローチ方法を学び、みなさんの施術の幅が広がったと思います♪ その調子でどんな人でも治療できる医療人になってくださいね! 次回以降もレポートをお届けします! お楽しみに!! 「本物の技を磨くなら日本医専」 一度、日本医専の技を見に来ませんか? 日本医専では他にも様々なイベントを開催しています。 興味のあるイベントにぜひお越しください♪ ★柔道整復学科★ 10/3(日)13:00~15:00「スポーツトレーナーの仕事<柔道整復師・鍼灸師>」 10/9(土)14:00~16:00「意外と知らない接骨院での働き方」 10/17(日)13:00~15:00「あなたの可能性を広げる「4大柔整」を知ろう!」 10/23(土)14:00~16:00「スポーツトレーナーの仕事を体感しよう!」 10/30(日)13:00~15:00「はじめてのスポーツ柔整」 ★鍼灸学科★ 10/3(日)13:00~15:00「やさしい鍼でリフトアップ!美容鍼灸の効果」 10/9(土)14:00~16:00「基礎からわかる美容鍼灸 ~綺麗なすっぴん素肌の作り方~」 10/17(日)13:00~15:00「徹底解説!日本鍼灸と中国鍼灸の魅力」 10/23(土)14:00~16:00「スポーツ・美容・婦人・高齢者 ~4大鍼灸を知ろう!~」 10/30(日)13:00~15:00「耳ツボダイエットと美容鍼灸」 皆さまのご参加を心よりお待ちしております! ★まずは日本医専を知ろう!★ ≪日本医専の資料請求はこちら≫]
-
 2021/09/17コラム
2021/09/17コラム- 【片橋先生コラム・第12弾】~もうひとつのオリンピック~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第12弾! もうひとつのオリンピック みなさん、こんにちは。柔道整復学科専任教員の片橋です。 暑さが急に和らぎ、長袖を着る日もでてきました。 いかがお過ごしでしょうか。 夏の大きなイベント東京2020オリンピックが終わりました。1年延期して開催国である日本が緊急事態宣言の中、ほぼ無観客で開催という異例のオリンピックでしたね。 さて、みなさんはオリンピックの起源をご存知ですか? そう、古代ギリシャですね。 ギリシャ神話に出てくるゼウスをはじめ多くの神々を崇めるオリンピア信仰の宗教行事だったのです。 全裸で行っていたため、出場者は男性だけ。戦車競技があったなんて話を聞いたことがあるかもしれません。 この古代オリンピックは何と紀元前9世紀ごろから393年の第293回、1169年間も受け継がれたそうです。 今回の東京オリンピックは第32回です。 近代オリンピックのはじまりは1896年で第1回大会はオリンピック発祥の地ギリシアのアテネで開催されました。 復興を提唱したのはフランスのピエール・ド・クーベルタン男爵。 NHKの大河ドラマ『いだてん~東京オリムピック噺~』で覚えている方も多いでしょう。 ではアジアで最初のIOC委員となったのは?はい、嘉納治五郎先生ですね。 柔道の創始者ですね。 柔道整復師には柔道がついていますから、もちろん関係があります。 さらに新しいのが1960年に第1回と位置づけられたもうひとつの(Parallel)+オリンピック(Olympic)、パラリンピックです。 第2回は1964年の東京大会です。 はじまりは1948年、医師のルードウィッヒ・グッドマン博士の提唱によって、ロンドン郊外のストーク・マンデビル病院内で開かれたアーチェリーの競技会です。 第2次世界大戦で主に脊髄を損傷した兵士たちの、リハビリの一環として行われたそうです。 「リハビリテーションrehabilitation」はなじみのある言葉ですが、医療の分野では非常に新しく、正確な意味も一般には伝わっていません。 re(再び)+ habilis(適した)はすなわち再び適した状態になることで、復職、復権、名誉回復と訳されます。 体の機能回復にとどまらず、病気や犯罪からの社会復帰、壊れた建物の復旧など非常に広い意味で用いられているのです。 東京2020パラリンピックの大きなテーマが多様性でした。アスリートも彼らの支援者も大会の運営者も同じ目標に向かってそれぞれのカラーでキラキラと輝いていました。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]
-
 2021/09/10コラム
2021/09/10コラム- 浮谷先生コラム 第11弾 ~Birthday Olympic~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 浮谷先生コラムの第11弾をお届けいたします! 皆さんこんにちは。専任教員の浮谷です。 このブログは9月5日深夜から6日にかけて~東京パラリンピック2020が閉会式を迎えた日から記しています。 すでに先月、東京オリンピック2020や甲子園の高校野球大会も幕を閉じました。 コロナ禍で心配される中、今年の《スポーツの夏》も終わりが近づき、「オリパラ・ロス」というのでしょうか? テレビで観戦疲れの人もいるかもしれません。 今回は去り行く夏の大会を惜しみつつ、Birthdayネタで少々お付き合いください。 前回、私のブログでは年齢を隠さず「初老の哀感?」を漂わせていました。 申し遅れましたが自身のBirthdayは6月14日です。 ご存じのようにネットの時代になって、その日にどんなことがあったのか?すぐわかるようになりました。 そこでこの日の出来事~《今日は何の日》からOlympicや医学に関する当時の記録を取り上げてみたいと思います。 Olympic関連で申しますと、6月14日は 1914年(大正3年):「五輪旗制定記念日」 パリで開かれたオリンピック委員会で5色のオリンピック旗(五輪旗)が制定されました。 国旗で言いますと時代がさらに遡りますが 1777年:「フラッグデー」~アメリカ合衆国 アメリカ合衆国議会がこの日、星条旗をアメリカ国旗と制定しました。 日本のニュースでは 1940年(昭和15年):勝鬨橋(かちどきばし)が完成‼ これには少々解説を要します。 1940年直前の日本は「紀元2600年記念行事」の一環として帝都・東京でオリンピック1940と日本万国博覧会1940を開催すべく準備をしていました。 2つの国家的イベントのシンボルとしてこの日、可動橋「勝鬨橋」が完成したのです。 しかし残念ながら2つとも日中戦争の激化等で開催中止になってしまいました…。 記録によれば当初から両大会は現在の月島・晴海会場を設定し、銀座方面から隅田川を渡って入場する言わばオープニング・ゲートとしての役割を勝鬨橋は担っていたわけです。今回のオリンピックで言えば「高輪ゲートウェイ駅」と同じですね! 今や「開かずの橋」になってしまった勝鬨橋ですが「幻の東京オリムピック1940」「幻の日本萬國博覧会1940」のシンボルとして現在に至っております (注/オリムピックや萬國と記載すると、1940年の東京大会を意味するそうです)。 長くなってしまいました。続いては医学関連で2つほど。 「認知症予防の日」:医学者・精神科医であり、「アルツハイマー病」発見者のアロイス・アルツハイマー(1864年/ドイツ)の誕生日に由来して日本認知症予防学会が制定しました。 「世界献血者デー」:病理学者で「ABO式血液型」を発見したカール・ラントシュタイナー(1868年/オーストリア)の誕生日に由来して国際赤十字連盟や国際輸血学会などが合同で制定しました。 おまけ/前回のブログで『東京物語』~小津安二郎監督作品を紹介しましたが、映画がらみでもう1点、 1949年(昭和24年):映倫発足の日 この日、映画倫理規定管理委員会(映倫)が発足したことに由来します。ちなみにこの年の 小津監督作品は『晩春』!キネ旬第1位の名作です。 以前も記したことですが、皆さんもご自身のBirthdayを調べるときっと面白い発見がありますよ。 (監修/浮谷英邦先生:歯科医師・介護支援専門員) >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら]
-
 2021/09/03コラム
2021/09/03コラム- 川崎先生コラム 第11弾「パラリンピックがきっかけで発展したスポーツ車いす」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川崎先生コラムの第11弾をお届けいたします! 東京パラリンピックが開催されて終盤を向かえていますが、様々な競技を応援していると困難があっても向き合い乗り越えようとする力と精神力に私自身も気持ちを駆り立てられました。 一番、感動したのはアスリート達の緻密な戦略と工夫で挑戦し続ける姿です。 テレビを観ていると心が熱くなり、今の私は挑戦し続ける思いや行動を忘れてしまっているなと、今までの自分そしてこれからの自分を顧みるきっかけとなりました。 そして、注目したのが車いすです。 選手の脚となり活躍しその機能や形態が進化していることです。また、選手の車いすの操作技術も凄いと感じました。 車いすの歴史 車いすの発祥については明確な背景がありませんが、車いすの原型は16世紀にヨーロッパで生活の中で使用されることがきっかけとなり知られるようになりました。 有名なのはスペイン王フィリップⅡ世が使用していた1595年に作られた下肢障害者用の車いすです。 4つの小型の車輪があり、リクライニングや小型の車輪が付いており、挙上式のフットサポート機能を備えた介助型の車椅子です。 その後、進化して18世紀にデザインも美しくなり駆動方式になりました。 19世紀に自転車が大流行したことで、現在の原型となる大車輪を駆動して自走できる形に変化し、ゴム製の車輪となり屋内、屋外の移動が快適にできるようになったといわれています。 日本では鎌倉時代に使用しているのがみられたといわれ、国産の車いすの製造は大正時代とされています。 スポーツがきっかけで車いすが発展 日本の戦後は、障害をもつ方が社会復帰をすることは余り考えられていなかった時代でしたが、1964年(昭和39年)に開催された東京パラリンピックで来日した海外の選手が自立した生活を送り、車いす自体も高度な機能を備えていることに影響を受け、それがきっかけとなり日本でも改革が進められるようになりました。 そしてこの頃にリハビリテーション医学が導入され医療機器として発展していきました。 スポーツで使用する車いすの種類 競技用の車いすは日常で使用する車いすとは異なり、競技の特性に合わせた形状や機能をもちます。 また、選手の身体機能を補うようにオーダーメイド仕様となっています。 [陸上競技用車いす] マラソンなどで使用されるレーサーという車いすです。 車体は軽く空気抵抗を受けにくい前輪が前方に出た3輪タイプで高速走向が可能な仕様になっています。 [バスケットやラグビー用車いす] バスケットやラグビーでは、選手同士が激しくぶつかり合う競技でもあり前方にバンパーが付いているのが特徴です。 ラグビーで使用されている車いすは選手みんなが同じ様式の車いすかと思っていましたが、攻撃型と守備型で形が異なります。 みなさん気付いていましたか? [テニス用車いす] テニスなどターンやダッシュなどの動きが多く小回りが必要な競技では、車輪が斜めに設計されているのが特徴です。 特にテニスでは、車輪の角度が大きくサーブなどで転倒しないように車いすの前後に小さな車輪が付いています。 スポーツ用の車いすは今でも進化し続けています。 フレームやハンドリム(駆動輪のを回転させる部分)は動きに強く、かつ柔軟性がある素材が使用され軽量化されています。 最も大事なのは選手が座るシートだそうです。 選手が座るシートの高さや膝のポジションによりタイムが変わるといわれています。 車いすも体の一部なので各選手に合わせたものが必要なのですね。 私たち柔道整復師は、臨床現場で車いすを使用する患者様のサポートをすることがあります。 安心して快適に使用してもらえるように配慮していきたいと思います。 最近、日本医専のお母さんと認められた私です。 もうそんな年齢になったんだな~と思いながら、日々学生の心配をしています。 学生はみんな素直でいい子ばかりです。 少し手が掛かるところもありますが夢に向かって頑張って欲しいと思います。 日本医専のお姉さんと呼ばせるために超音波美顔器を購入しました。 効果の程はわかりません。(本当は肌荒れが気になるから買ってみました。(*^-^*)) お姉さんと言われたら効果が出ているのだと・・・・・思います。 本校柔道整復学科専任教員 柔道整復師・鍼灸師 川崎有子 >>資料請求はこちら >>日本医専のイベント情報はこちら >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら]
-
 2021/08/27コラム
2021/08/27コラム- 【片橋先生コラム・第11弾】~打撲~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 片橋先生によるコラム・第11弾! 打撲 みなさん、こんにちは。はじめまして。 柔道整復学科専任教員の片橋です。 深刻なコロナ禍の中、無事にお過ごしでしょうか。 毎日心配ですね。 手洗いや消毒、うがい、マスク、外出を控える、睡眠、栄養バランスの整った食事といった感染対策の基本を徹底して、各人が地道に自分の身を守っていくことが大切ですね。 「打撲」は「だぼく」と読み、柔道整復師の仕事(業務範囲)です。 一般的には打ち身と呼ばれ、日常生活でよく起こるケガです。 転んだりぶつかったりして外から体に力がかかり、力がかかったところが損傷し、傷口を伴わないものが打撲です。 とても身近なケガで、骨を除いた全身の体の軟らかい部分(軟部組織)のどこにでも起こります。 あしを椅子に少しぶつけたような軽いものから、頭やお腹をぶつけて脳や内臓を損傷するものまで程度がさまざまです。 災害時、瓦礫の下に何時間も体が押しつぶされる挫滅症候群(クラッシュシンドローム)では命の危険もあります。 傷口はありませんが、中では出血しているため腫れます。 よかれと思って一生懸命にもむ人がいます。 こうすると中の血の塊が刺激され、骨になってしまうことがあります。 これを骨化性筋炎といいます。 打撲をしたら、冷やします。 湿布では冷やす力は弱いので、氷や保冷剤を使います。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) >>柔道整復学科の過去のコラムはこちらから >>本校の資料を請求する場合はこちらから >>オープンキャンパスや説明会についてはこちらから]
-
 2021/08/26コラム
2021/08/26コラム- 【コラム】マラソンや駅伝のコンディショニング
-
こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校です。 もうすぐ秋ですね。 今年は東京マラソン大会も開催が予定されておりマラソンのシーズンの到来です。 そしてお正月には実業団駅伝や箱根駅伝など日本人に深く愛される駅伝のスポーツ中継が新年の定番ですね。 今回のテーマはこれからシーズンを迎えるマラソンや駅伝についてです。 マラソンのコンディショニングや駅伝の魅力についてお話ししたいと思います。 1、マラソンに参加する前のコンディショニング 普段ランニングしている方もマラソン大会前にはケガや故障、そして当日棄権をしないためにも準備が大切です。 まずは当日のコンディショニングを整えるための5つのポイントをご紹介します。 ① 本番にむけてしっかり準備をしておく コンディショニングで一番重要なことは本番に向けて準備をしておくということです。 そして本番や大会直前に初めてのことをやらないということも大切です。 例えばトレーニング法・食事・治療などこれまでに試したことがないことを急に試してしまうことによってコンディショニングに悪影響がでてしまう可能性があります。 これまでトレーニングで積み重ねてきた力を発揮して、楽しいランになるように本番に向けてしっかりと準備をしておきましょう。 ② マラソンに必要な食事を摂る マラソンのように持久力が必要なスポーツでは、スタミナを保つために炭水化物を多めに摂る食事法があります。 炭水化物を多く食べることで、体内でエネルギーの素となるグリコーゲンが効率よく蓄えることができます。 マラソン当日の3日前くらいからは油の多い食事は控えめにして、ご飯や麺類など炭水化物が多めの食事がおすすめです。 ただし、極端に食べ過ぎてしまうと体が重たくなって走りにくくなることもあるので気を付けましょう。 また、炭水化物のほかにタンパク質もプラスするとさらに理想的です。 炭水化物の多いカステラ、糖質のあるバナナなどの果物、タンパク質も含まれているココアなどもおすすめです。 ③ 準備は前日までに済ませておく 前日の準備といってもいろいろあります。 まずは、体調面。 前日は意識していなくても緊張していることがあります。 胃腸に負担のかかる食事やこれまでお腹を壊してしまったメニューなどが避けましょう。胃腸を冷やす冷たい飲み物や利尿作用のある緑茶やコーヒーも控えめにするといいでしょう。 そして、道具の準備。 当日の朝にスムーズに出発できるように荷物は前日までに準備しておきましょう。 特に天候予報はよく確認してウエア調節や冷え防止のためのカイロの準備など事前に用意しておくと安心です。 ④ 当日の寒さ対策も万全に マラソン大会は秋から冬のシーズンに開催されることが多いので、寒さ対策も必要です。 体が冷えないように温かい服装で会場に行くとよいでしょう。 会場では冷えやすい太ももの内側、腰、膝のマッサージをして血行をよくするなど、走り出しをスムーズにすることもポイントです。 2、駅伝の魅力 ここではコンディショニングの話題だけでなく、駅伝の魅力についてお伝えしたいと思います。 駅伝もマラソンと同じく中長距離を走るスポーツですので、コンディションはマラソンと同様です。 マラソンとは違う駅伝の魅力は、襷(たすき)をつなぐということでしょう。 人気の箱根駅伝はまさに母校の襷をつなぐリレーであり、1人20㎞を超える距離を走り、それを10人でつなぐことに毎年ドラマが起きるのです。 チームのエースが快走したとしても、途中1人のコンディショニングが悪くて完走できなければチームの記録が残らないのです。 全員が全力を尽くして成果を出すスポーツです。 ただ、駅伝は団体戦とも言えません。 あくまで走るのは個人であり、誰の助けも借りずに1人ただひたすら使命感を持って走るのです。 前の選手から受けた襷をひたすら次の選手につなぐために全力で走り、襷をつなぐと倒れこむというシーンもあります。 まさに使命感からの解放の瞬間なのかもしれません。 駅伝もまたマラソンと同じく日々の練習と大会に向けたコンディショニングが勝敗を分けるのです。 スポーツには欠かせないコンディショニング。 本番前のケガを防ぎ、全力を発揮できるように意識して取り組みたいですね。 そして、スポーツ後のメンテナンスも忘れずに。楽しく体を鍛錬しましょう! <<ほかの柔道整復学科ブログはこちら>>]
- お問い合わせ
- info@nihonisen.ac.jp
- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30
- LINEで問い合わせる







