-
 2020/12/09その他
2020/12/09その他- 坐骨神経痛とは
-
こんにちは。日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 関節痛には、腰痛・四十肩五十肩・変形性関節症・膝の痛み・坐骨神経痛などがあります。 今回はその中から「坐骨神経痛」について説明します。 1、坐骨神経痛とは? そもそも「坐骨神経痛」は、病名ではありません。 神経痛が下肢にあらわれる症状の総称で、おしりから下肢(あし)にかけて痛みやしびれが続く状態のことをいいます。 坐骨神経は、坐骨を通っておしりの筋肉を抜けて足に向かう未梢神経のひとつで、未梢神経は脳と脊髄からなる中枢神経と体の各部を結んでいます。 そのため、体を動かしたり、温度を感じたりする伝導路の役割をしていて、おもに3つの神経から構成されています。 足を自由に動かせたり、バランスよく歩くことができるのは、未梢神経である「坐骨神経」がしっかり働いてくれるからなのです。 ちなみに坐骨神経は、太さはボールペンくらいで、長さは1mくらいです。 この長い坐骨神経は腰椎から足の指まで伸びているので、坐骨神経痛になるとおしりから下肢かけて痛みがでてしまうのです。 2、坐骨神経痛の症状 「坐骨神経痛」の痛みは、痛みとしびれがあり、本人はとてもつらい症状です。 痛みは、「ズキズキ」を感じますし、しびれは、「ビリビリ」「チクチク」「ジンジン」を感じることが多いようです。 この痛みは、おしりから下肢にかけて起こり、片足に症状がでることが多いですが、場合によっては両足に痛みやしびれを感じることもあります。 《坐骨神経痛のおもな症状》 ①おしりから下肢にかけて痛みがある ②長い時間立っていることがつらい ③腰を反らすと下肢に痛みやしびれを感じることがある。 ④おしりの痛みが強く、座り続けることができない、もしくは困難に感じる ⑤歩くと足に痛みが出るため歩けなくなったり、時々休みながらであれば歩ける。 ⑥体をかがめると痛みが強くなる このような症状が1つでもあてはまると、坐骨神経痛の可能性があります。 3、坐骨神経痛が起こる原因 坐骨神経痛を引き起こしている原因がさまざまありますが、主な理由は「椎間疾患」で、その中でも、「腰部脊柱管狭窄症」と「椎間板ヘルニア」です。 これから加齢によって引き起こされる場合もあります。 筋肉量は20代をピークに減少していきますが、最も衰えが早いのが下肢の筋肉です。 下肢に加えて、おしりの筋肉の衰えが原因になっていることもあります。 4、坐骨神経痛の治療法 坐骨神経痛の痛みが出てしまったときには、「保存療法」と「手術療法」の2つの治療法があります。 とくに「保存療法」では、生活習慣やライフスタイルにあわせて治療をおこないます。 《坐骨神経痛の治療法(保存療法)》 ①マッサージ療法や低周波電気療法などの温熱療法 ②体操やストレッチなどの運動療法 ③コルセットなどの装具療法 ④薬を使って痛みを和らげる薬物療法 ⑤局部麻酔や抗炎症剤を直接注入するブロック療法 5、坐骨神経痛の予防 坐骨神経痛の改善には治療や筋肉アップも大切ですが、腰の負担を和らげる日常生活を心がけることも大切です。 そのほかに、禁煙することも効果的です。タバコは血管を収縮させて酸素や栄養の供給を阻害してしまうため、痛みが悪化してしまう原因となるため、禁煙によって血行を良くすることで痛みの改善にもつながります。 坐骨神経痛は、生活習慣を見直すことで予防・改善につながります。 日々の生活では、正しい姿勢を保つ・冷えを防ぐ・ストレッチを行うなど、腰に負担をかけない生活行動と適度な運動を心がけましょう。 少しでも気になる症状や違和感がある場合には、早めに医療機関の受診をおすすめします。 <<柔道整復師の仕事についてはこちら>> <<柔道整復学科のオープンキャンパスはこちら>> 皆さまのご参加を心よりお待ちしております!!]
-
 2020/11/20ゼミ活動
2020/11/20ゼミ活動- 【スポーツゼミ】「東京高等学校で現場実習をしてきました」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 スポーツゼミで定期的に行われている現場実習! 今回は東京高等学校へ行かせていただきました。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 東京高等学校のラグビー部で三田先生がトレーナーとして活動しているので、今回は一緒に間近でトレーナー活動を体感しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 この日は練習や試合でケガをしてしまった選手のリハビリトレーニングをスポーツゼミの学生がサポートするといった内容です! まずは2人一組に分かれて、選手を1人ずつサポート!! ケガといっても腰や脚など様々なので、選手に合わせて効果的なリハビリトレーニングをやっていきます。 三田先生は全体を見て回って選手やスポーツゼミの学生にトレーニングの効果や意識するポイントを教えていきます。 スポーツゼミの学生も一緒になってトレーニングに参加! リハビリトレーニングでもなかなかキツそうでした… 三田先生もスポーツゼミの学生も選手一人ひとりにちゃんと寄り添って対応していて終始良い雰囲気の現場実習でした! 現場実習では学校で見られない頼りがいのある背中を見ることができました。 もっと大きな背中になれるよう頑張ってください!! 本校では、スポーツゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]
-
 2020/11/19学習支援
2020/11/19学習支援- 【柔道整復学科】国家試験個別補講を取材しました!
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は柔道整復学科の国家試験個別補講を取材してきました! 国家試験当日まで残すところ約100日と迫った今、「全員合格」を目指して本校では個別の対応に力を入れています! 具体的には実力試験結果などより学習支援が必要な方を探してグループ分けをし、まずは自分達の力で解決を目指す「グループ学習スタイル」を中心に、教員そしてチューター(お手伝いに来てくれた卒業生)が適宜フォローに入っています。 「今日できない問題を今できるようにする」 これから国家試験までの日々はこの繰り返しです。 同じ目標に向かって頑張っている仲間の姿は、背中を押してくれる大きな力となってくれます。 住吉先生のアイデアで生まれた『オンラインマークシート』。 QRコードを読み込んで、オンラインマークシートに4択問題を回答していきます。 学生さん同士でも教え合って、教えてもらう方も教える方も相乗効果で学力アップ! 自分たちで解決できない時は、すかさず教員が助っ人に入ります!! 受験生の皆さんは、毎日精一杯頑張っています。 日本医専も『全員合格』を合言葉に最後の最後まで全力で応援していきます!! <<日本医専の柔道整復学科についてはこちら>> 週末にはオープンキャンパスも開催しております! <<日本医専のオープンキャンパス情報はこちら>>]
-
 2020/11/17未分類
2020/11/17未分類- 高齢者の健康に関わる柔道整復師~柔整介護~
-
こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 今回は、柔道整復師が老人ホームやデイサービスなどの介護施設でどう活躍しているのかをご紹介いたします。 1、柔整介護 柔道整復師は機能訓練指導員として介護施設でも活躍しています。 実際に柔道整復師の国家資格を取得するための授業の中でも、高齢者の身体的特徴や変化を学びます。養成校によっては高齢者デイサービスだけでなく、特別養護老人ホームで臨床実習をおこない、実際の現場で体験学習をおこなっています。 柔整介護では、高齢者外傷予防を含むさまざまなことを学んでいます。 ・高齢者の健康 ・ロコトレ(ロコモーショントレーニング) ・運動器の健康 ・転倒予防 ・機能訓練トレーニング など 2、高齢者の骨折は寝たきりの原因 高齢者の健康に関わることとして、「骨折」が挙げられます。 高齢者の骨折は、骨粗鬆症による骨の脆弱化が基礎にあります。 わずかな外力でも骨折してしまうことが特徴で、一度骨折してしまうと長期間の安静で「寝たきり」の原因になってしまう可能性もあります。 そして、高齢者が骨折する原因のほとんどは「転倒」です。 3、高齢者に多い骨折と治療法 高齢者が転倒したときに骨折しやすい部位は4か所あります。 ①太ももの付け根(大腿骨近位部骨折) 転倒によって最も骨折しやすい部位で、寝たきりになってしまう方も多いため、社会問題にもなっています。 ②背骨(脊椎圧迫骨折) 尻もちをつくことで起こりやすい骨折です。骨粗鬆症が進むと日常の生活動作でも骨折してしまうことがあります。 そのため、「いつのまにか骨折」と言われることもあります。 ③腕の付け根(上腕骨近部位骨折) 転んだときに肩を打ったり、肘や手をついたときに骨折してしまいます。 ④手首(橈骨遠位端骨折) 転んで手をついたときによく起こる骨折です。 このように高齢者は日常生活での転倒によって骨折しやすいことがわかります。 骨折の治療はおもに手術療法と保存療法となりますが、治療が長期の安静を要したときには、以下のことに気を付ける必要があります。 ・筋力低下 ・認知症 ・肺炎 ・褥瘡(床ずれ) いずれも寝たきりになる頻度が高いことがわかっているため、早期のリハビリで回復機能を図ることの重要です。 4、高齢者の健康予防 このように高齢者が日常生活を元気に過ごすためには、骨折予防が何より重要です。そのためには骨粗鬆症のケアに取り組むことがよいでしょう。 たとえば、定期的に検診を受ける、カルシウムなど必要な栄養素を適量摂取する、内服薬や注射薬など治療をして進行を抑えるなどです。 また、柔整介護でもお話ししたロコモティブシンドロームのチェックを行い、転倒しやすいかを把握したり、転倒しないような生活環境を整備することも必要です。 骨や関節の病気は死に至るわけではありませんが、生活の質を著しく落としことに繋がります。寝たきりになると、認知症にも繋がります。 元気に動けるということが、その方の「健康寿命」に大きく関係します。 柔道整復師は高齢者が健康で元気に動けるように骨折予防にも積極的に関わっていける職業です。 人生100年時代に「柔整介護」での活躍が益々注目されていくでしょう。 イベントでは柔道整復学科や柔道整復師の仕事についてご紹介しております <<柔道整復学科のイベント情報はこちら>> みなさまのご参加を心よりお待ちしております!]
-
 2020/11/13ゼミ活動
2020/11/13ゼミ活動- 【ケガゼミ】ボクサー骨折の固定
-
こんにちは!日本医学柔整鍼灸専門学校広報担当です。 本日は4大柔整ゼミのひとつ、「ケガゼミ」についてのレポートです。 本日のテーマは【ボクサー骨折】。 中手骨頚部の骨折で、多くがパンチ動作で発生するためボクサー骨折とも呼ばれます。薬指や小指の中手骨によく発生します。 ペアで患者役と固定する役とわかれて実技を行っていきます。 形を整えるのに苦戦する学生たちは、何度も固定器具を微調整。 「難しいでしょ?こうやってやるんだよ」とケガゼミ顧問の横山先生。 奥田校長も直接学生に指導。 苦戦しながらも先生に質問をしたり、学生同士で教え合ったりと和気あいあいとした雰囲気のゼミ活動でした。 ケガゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! ゼミについて詳しく知りたい方はぜひオープンキャンパスにご参加ください♪ >>オープンキャンパスについてはこちら >>過去のゼミ活動の様子はこちら]
-
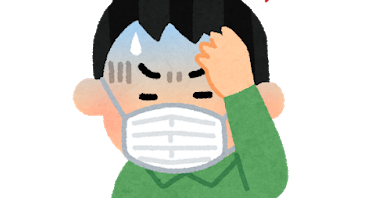 2020/11/13未分類
2020/11/13未分類- 「マスク肩こり」・「マスク頭痛」の対処法
-
1、「マスク肩こり」「マスク頭痛」とは? 新型コロナウイルス感染症対策でマスク着用が、日常となりました。 そして、秋になり雨が多くなる季節柄 ジメジメして疲れを感じやすく体調を崩しやすい気候です。日中の大半をマスク生活で過ごしているため、マスクを長時間つけていることによって、首肩がこる、頭痛がする、噛みしめや食いしばりといった症状が出る方も多いようです。 さらにはマスク生活では息苦しさからマスク疲れも感じます。 このようなマスク生活で多くの人は感じているのが『マスク肩こり』と『マスク頭痛』です。 これまでも普段からマスクを着用していた方、職業柄マスク着用をしていた方など慣れてしまっている方はいいのですが、これまでマスクを着用していなかった人の体に不良が現れてきているようです。 2、「マスク肩こり」「マスク頭痛」の原因 マスクを長時間着用することによる『圧迫』と『酸欠』の2つが大きな原因と考えられます。 ●『圧迫』 マスクを長時間着けていると、耳にかけるゴムによって耳のまわりや側頭部の筋肉が引っ張り続けられています。それによって圧迫されて血行が悪くなったり、側頭から耳のまわりの筋肉が緊張して、緊張型頭痛を起こしてしまうのです。 緊張型頭痛だけでなく、耳の裏があかぎれのようになって出血してしまったりする方もいるようです。 ●『酸欠』 マスクをしていると呼吸がしにくいため酸欠状態になります。 血中の酸素濃度は下がり、二酸化炭素濃度が増えます。二酸化炭素には血管を拡張させる作用があるので、顔周りに熱がこもり、血流が良くなることで血管が拡張して頭痛が起きてしまうのです。 マスクによる息苦しさで口呼吸になってしまい、マスクの中で口や鼻が覆われて表面的だけの呼吸になってしまいがちです。そのせいで体調の変化を感じてしまう方も増えているようです。 酸欠が続いてしまうと、頭痛やめまい、自律神経の乱れによって疲れやすくなったり、集中力の低下にも繋がります。さらには全身が酸欠状態になると体だけでなく、メンタルにも不良を感じるようになりストレスも原因にもなってしまいます。 このほかにも、マスクで熱がこもって顔の温度が上がって頭の血管が拡張することで片頭痛がでやすくなってしまうこともあるようです。 3、「マスク肩こり」「マスク頭痛」の予防には マスク着用の日常生活でも改善予防できるように気を付けましょう。 ①耳に負担の少ないマスクを選ぶ ②マスクを外せる時には外し、定期的に深呼吸をする。 ③自立神経の乱れを整える。 ④マッサージやストレッチでコリをほぐす。 4、具体的な予防策とは ①耳に負担の少ないマスクを選ぶ マスクもいろいろな種類のものがあります。自分に合ったサイズ、ゴムの柔らかいもの、通気性のよい負担の少ないものを選ぶと良いでしょう。 ②深呼吸をする。 酸欠を防ぐためにマスクを外せるときには外して、深呼吸をしてみましょう。 ③自律神経の乱れを整える。 自律神経が乱れると体に不調を感じます。 不規則な生活やストレスよって自律神経の働きが乱れると、筋肉が緊張して、頭痛やめまいの原因となることも多いです。片頭痛に対しては、自立神経を整える鍼灸での治療がおすすめです。コロナ禍でも自立神経が乱れないように、睡眠・食事・適度な運動など規則正しい生活をしましょう。また、入浴時にはゆっくりと湯舟に浸かることもおすすめです。 ④マッサージやストレッチをしてコリをほぐす。 頭痛や肩こりには、ストレッチやマッサージ、運動で症状は緩和・改善されたりします。頭の横に痛みがある場合には、耳のマッサージがおすすめです。耳をつかみ、上下前後と痛くない程度に引っ張りながら動かしてみると、固まった筋肉が緩み、痛みが緩和されます。痛みがひどいときにはプロから頭部・首・肩の痛みと取る施術を受けるのもいいですし、痛みの出にくい身体作りを教えてもらうのもいいでしょう。鍼灸やオイルマッサージで筋肉をほぐすと解消することができます。 感染症予防のために、マスク着用の日常はまだ続きそうです。 夏は猛暑でマスクをつけることでストレスになることも多かったですが、ワクチン接種が進んでもまだまだマスク生活は続きそうです。 そして、冬の季節は寒さで筋肉が固まりやすく、肩こりや頭痛が起こりやすくなります。 まだまだ終わりの見えないマスク生活です。自分なりの対処法を見つけて、疲れやストレスを溜めないように上手につき合っていきましょう。 授業、ゼミの様子やコラムが盛りだくさん! >>ほかの柔道整復学科コラムはこちらから まずは日本医専について知ろう! >>日本医専の資料請求をする]
-
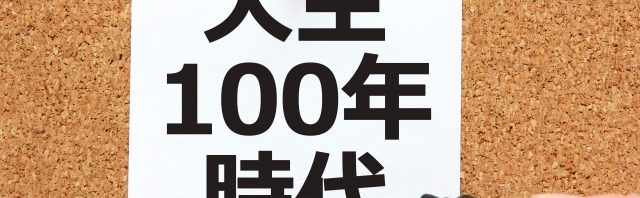 2020/10/26その他
2020/10/26その他- 『予防と健康』~支援・介護に頼らず生きるために~
-
こんにちは。日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 人生100年時代と言われる現代で、長寿にともなって支援・介護による医療費や介護費は年々増大しています。 そして、長寿だけではなく、『健康長寿の延伸』が社会全体の大きなテーマであり、要支援、要介護の原因である関節疾患(いわゆる足腰)も健康寿命を延ばすことの要因のひとつと言えるでしょう。 1、健康寿命とは 健康寿命とは、「心身ともに自立し、健康に生活できる期間」のことです。 2000年にWHO(世界保健機構)が提唱して以来、「寿命を延ばす」という従来の指標に加えて、「健康でいられる期間を延ばす」という健康寿命の指標が重要視されるようになりました。 2、健康寿命と平均寿命の違い 健康寿命とよく比較されるのが、「平均寿命」です。平均寿命とは、0歳のときに何歳まで生きられるかを統計的に予測した平均余命のことです。 健康寿命との違いは、日常生活に制限のある「健康ではない期間」も加えられるということです。 厚生労働省が2019年に発表した日本人の平均寿命は以下の通りです。 女性:87.45歳 男性:81.41歳 いずれも過去最高を更新しており、女性が7年連続、男性が8年連続を更新しています。 3大死因である【がん】【心疾患】【脳血管疾患】による死亡率が改善したことが長寿化の要因です。 一方で、厚生労働省が2018年に発表した健康寿命は以下の通りです。 女性:74.21歳 男性:71.19歳 男女ともに、平均寿命から9年以上の開きがあることがわかります。 日本人は平均寿命の数値は年々増加傾向にあるものの、高齢者が人生を最後まで自立して生活を送るという理想的な長寿社会にはまだまだ課題があるようです。 3、健康寿命を延ばすための取り組み 健康寿命に影響するのは、3大死因だけでなく、『関節疾患』があります。 支援や介護なく自立した生活を送られる期間が健康寿命でもあり、人生100年時代の到来で、健康寿命の延伸があってこそQOL(クオリティ オブ ライフ)の向上は実現します。 厚生労働省の公開した統計によると、介護が必要となったおもな原因は要介護別に、要支援者では「関節疾患」が19.4%と最も多くなっています。 要介護者では脳卒中などの「脳血管疾患」が24.1%と最も多いです。 関節疾患が悪化すると運動が困難となり、脳血管疾患の原因でもある高血圧や肥満を誘発することにも繋がり、やはり関節疾患を未然に防ぐことは健康寿命の延伸になると言えるでしょう。 2011年から日本では「健康寿命をのばしましょう。」とスローガンに、国民全体が人生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目標とした『スマート・ライフ・プロジェクト』という取り組みを推進しています。 『スマート・ライフ・プロジェクト』とは? ①適度な運動 生活習慣病の予防には男性9000歩、女性8000歩が目安といわれています。 また、苦しくならない程度にスピードをあげて早歩きすることも生活習慣病の予防に効果があります。 ②適切な食生活 日本人は1日平均で約280gの野菜を摂っていますが、生活習慣病予防のためには1日あたり350gの野菜が必要です。 ③禁煙 タバコは4000種類もの有害物質が含まれており、タバコを吸うことは健康を損なうだけでなく、肌の美しさなども繋がります。健康寿命を延ばすためには禁煙が好ましいです。 4、健康寿命を延ばす地域のプロフェッショナル このように健康寿命を延ばすには、日頃からのケアが大切です。 たとえば、関節疾患の治療として注目されているのが「接骨院」や「鍼灸院」です。 昔から地域に根差している「接骨院」や「鍼灸院」では、医療系国家資格である柔道整復師や鍼灸師が施術をおこないます。 人体について正しい知識を持つ柔道整復師や鍼灸師は、身体のチェックをしてくれる有益なプロフェッショナルです。 地域によってはコンビニと同じくらいあると言われている「接骨院」や「鍼灸院」を気軽に活用して、関節疾患になりにくい身体作りをするとよいでしょう。 医療費の削減にも繋がりつつ、なによりも日本人の健康寿命延命に活躍できる人材が、柔道整復師や鍼灸師などの地域で活躍する医療人なのです。 これらの活動は介護予防にもとても有効です。 心身ともに自立し、健康的な生活をするためには意識的にセルフケアをおこなって、楽しく長く生きることを目標に、今できることを考えて行動していくことが将来の健康につながるでしょう。 ▼オープンキャンパスでは柔道整復師や鍼灸師の仕事を紹介しています!▼ 10/31(土)14:00~16:00 <<【柔道整復学科】スポーツトレーナーになるには>> <<【鍼灸学科】やさしい鍼でリフトアップ!美容鍼灸の効果>> 11/8(日)13:00~15:00 <<【柔道整復学科】「ケガ」「スポーツ」「ヘルスケア」「高齢者ケア」4大柔整ゼミを知ろう!>> <<【鍼灸学科】鍼灸師×スポーツトレーナー>> みなさまのご参加を心よりお待ちしております!!]
-
 2020/10/21ゼミ活動
2020/10/21ゼミ活動- 【スポーツゼミ】「川崎市立橘高等学校で現場実習をしてきました」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 スポーツゼミで定期的に行われている現場実習! 今回は川崎市立橘高等学校へ行かせていただきました。 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら 橘高等学校のソフトテニス部で三田先生がトレーナーとして活動しているので、今回は一緒に間近でトレーナー活動を体感しました! 三田先生は鍼灸師資格、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー資格のみならず、NATA-ATC(National Athletic Trainers‘ Association)の資格を活かし、NFLサンフランシスコ49ersトレーナー、米国陸上選手タイソン・ゲイ氏(他、代表選手5名)のパーソナルトレーナーを務めるなど、第一線で活躍中の先生です。 この日は初めて現場実習が初めての1年生も多かったので、まず橘高校のソフトテニス部がどのような練習をしているのか体験してみようとのことで、フィジカルトレーニングに参加させていただきました! まずは5つのグループに分かれて下半身のトレーニング! 1グループにスポーツゼミの学生が1.2人混ざって一緒に練習していきます。 次に腹筋、腕立て伏せなどをしてから最後にランニングです。 スポーツゼミの学生は高校を卒業してから久しく運動していない人も多く、ヘトヘトになりながらも練習に参加していました。 練習が終わると、怪我や身体に違和感を感じた橘高校の学生たちが三田先生のところへ相談に来て、練習後のメディカルケア開始です! スポーツゼミにとってはここからが本番!! 三田先生のトレーナー活動をしっかりを見て学びます。 みんな違った症状なので、一人ひとりにちゃんと寄り添って笑顔で対応しているのが印象的でした。 皆さん三田先生のトレーナー活動を真剣に聞いていました。 終わった後も積極的に質問していて終始いい雰囲気の現場実習でした。 本校では、スポーツゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]
-
 2020/10/15ゼミ活動
2020/10/15ゼミ活動- 【スポーツゼミ】「足関節捻挫について」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校・広報担当です。 毎週木曜日は4大柔整ゼミのひとつ、「スポーツゼミ」の日! 【4大柔整ゼミとは?】 ケガゼミ、スポーツゼミ、ヘルスケアゼミ、高齢者ゼミの4分野に分かれて、より専門的な知識を学ぶことができる本校独自の学習制度です。 スポーツゼミでは、主にスポーツトレーナーとして活躍する際必要とされる知識や技術を学びます。 >>詳しくはこちら この日のテーマは「足関節捻挫について」 スポーツ現場だけではなく、普段の生活でも捻挫での痛みに悩む方も多いのではないでしょうか。 今回は2年生には事前に足関節捻挫について 「足関節捻挫とは何か」 「どこで発生するか」 「どんな症状か」 「どのように検査するか」 などを調べるように課題を出していたので、まとめたものを発表していきます! また、調べたうえで足関節捻挫について柔道整復師目線や鍼灸師目線でどういう治療法や予防法をやっていくかも発表しました。 実際に検査法や予防法も実践していきます 1年生は2年生の発表を見てレポートを書いていきます。 みなさん真剣な眼差しで先輩たちの発表を聴いて、質疑応答では積極的に質問していました。 発表していた2年生もそれを聴いていた1年生の皆さんも一生懸命に参加している姿が印象的なゼミでした! 本校では、スポーツゼミの見学も行っています。 参加希望の場合は、電話・メール・LINEにてお申し出ください! >>過去のゼミ活動の様子はこちら >>日本医専のスポーツトレーナー教育についてはこちら]
-
 2020/10/14ニュース
2020/10/14ニュース- 【コラム】骨折の種類
-
あなたは骨折をしたことがありますか? 骨折は、スポーツや交通事故、転倒などさまざまな場面で起こり得るケガで、誰にでもそのリスクはあります。 骨折と聞くと、枝が折れたり骨が変形したりと、一般的にそのイメ―ジもひとくくりにされがちですが、実際にはいくつかの種類があります。 ここでは、骨折の種類についてご紹介します。 1、骨折とは 骨折とは、その名のとおり骨が折れた状態です。 ただし、完全にポキッと折れた状態を想像してしまいがちですが、骨組織が完全に離断された状態だけが骨折ではなく、ヒビが入った場合や、骨の一部が欠けた場合、陥没した場合も骨折に含まれます。 例えば、整形外科や接骨院で骨にヒビが入っていると診断された場合、「骨が折れていなくてよかった。」と安堵する人もいるでしょう。でも、骨にヒビが入った状態はズレのない骨折です。実際には、骨の一部が欠けたり、つぶれたり、へこんだりするのも骨折に含まれます。 骨折は、その程度や症状によっても痛みの程度が違います。 骨自体には痛みを感知する神経がないので、骨折して痛いと感じるのは、骨の周りを覆う骨膜に痛みを感じる受容器が高密度に分布しているからです。 比較的軽症で治療期間が短くて済む骨折もあれば、強い痛みやしびれが起こる骨折もあります。骨折の程度や場所によっては、痛みを感じない場合もあります。 2、骨折の種類 「複雑骨折」や「疲労骨折」は聞いたことがあると思います。骨折にはいろいろな種類がありますので、ここでは代表的なタイプをご紹介します。 単純骨折(閉鎖骨折) 骨折した際に、皮膚表面から骨が露出していない状態の骨折のことを指します。 複雑骨折(解放骨折) 骨が折れると同時に、骨折した部分の皮膚も損傷して、骨が露出した状態です。 粉砕骨折 骨が粉々に砕ける骨折です。スポーツや交通事故による強い衝撃や、骨粗鬆症で骨が弱くなった人が転倒した場合などに起こりやすい骨折です。 疲労骨折 骨の同一部に継続的な力が加わることで折れた状態の骨折です。足や腰に起こるケースが多く、女性ホルモンの低下によって骨折する場合もあります。 圧迫骨折 骨がつぶれたように変形した状態の骨折です。腰や背中に強い痛みが出る場合が多く、老化や骨粗鬆症によって骨が弱くなると起きやすくなります。 剥離骨折 外部からの衝撃により、腱や靱帯の結合部分から骨が剥がれ落ちた状態の骨折です。日常的な動作が原因となり、手や足首に起こることが多いです。 皮下骨折 皮膚の下で骨折した状態です。外見ではわかりませんが、内出血にいるあざができてそのあとに変色します。 3、骨折の治療法 骨折の治療法は症状によって違います。大きく分けると「保存的治療」と「手術的治療」の2つがあります。 ①保存的治療 ギプスや添え木などを用いて骨折した部分を固定して安静を保ち、骨が癒合するのを待つ方法です。 骨では、骨を作る「骨芽細胞」と骨を壊す「破骨細胞」が常に働き、毎日生まれ変わっています。骨が折れても治るのはこうした身体のシステムが備わっているからです。 骨が折れて大きくずれている場合はうまく付着しないので、手や器具を使って皮膚の上からずれた骨や関節の位置を正しい位置に戻す「徒手整復」をしてからギプスなどで固定します。軽い骨折や疲労骨折の場合には、この保存的療法で対処するケースがほとんどです。治療は整形外科だけでなく、接骨院で柔道整復師による整復などもあります。 ②手術的治療 骨の損傷が著しい場合や、徒手整復ができなかったり、徒手整復してもすぐに元に戻ってしまう場合、体重がかかる足の骨などは、手術をおこないます。ネジやボルトで固定し、関節を動かしても骨が動かないようにするのが手術の基本です。整形外科など病院で治療することが多いです。 このように骨折はささいなことで誰にでも起こる可能性があります。 そのため、いざというときに、病院や接骨院に行く前に応急処置を知っておくといいでしょう。早く適切な処置ができるかどうかで、その後の状態を左右します。 骨折の疑いがある部位を固定して、安定が保てたら、患部を氷のうなどで冷やします。異常がみられたら、患部はむやみに触れないで、応急処置をして、速やかに医療機関で診断してもらいましょう。 柔道整復師の資格、仕事に興味のある方は下記ページからご確認ください。 >>柔道整復師の資格について >>柔道整復師の仕事内容 日本医専では、様々なイベントを開催しております。 興味のある方はぜひご参加ください。 >>申し込みはこちら >>資料請求はこちら]
- お問い合わせ
- info@nihonisen.ac.jp
- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30
- LINEで問い合わせる







