-
 2023/04/07コラム
2023/04/07コラム- 川﨑先生コラム 第35弾「新入生のみなさんに感動!!&友達を作ろう!」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第35弾をお届けいたします! 新入生のみなさんに感動!!&友達を作ろう! 新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。(*^-^*) 4月3日に、日本医学柔整鍼灸専門学校の入学式がありました。 新入生は少し緊張していましたが、希望に満ちた表情をしていました。 入学式の後は、新入生のオリエンテーションを行い、これからの学校生活のことや学習方法についての説明、クラスの友達と打ち解けるためのグループワークを行い楽しい時間を過ごしました。 新入生の魅力に感動!!■入学1日目 少しクラスの雰囲気を心配していましたが、とにかくみんな明るくて元気!元気! 友達とすぐに打ち解けていてインスタ交換して雰囲気は和気あいあいでした。 個性豊かなかわいい一面もたくさん感じることができました。 ■2日目のオリエンテーション 本校の教室に設置してあるMAXHUB(高性能なカメラ、マイク、スピーカー、パソコン、大画面タッチスクリーンが一体化となったオールインワンのミーティングボード)を使用して、『AIと柔道整復師』をテーマにグループワークを行いました。 少し難しいテーマですが積極的に意見交換して、発表も考えを簡潔明瞭に伝えてすごく上手でした。 柔道整復師として大切な人を「思いやりの心」や「温かさ」など患者さんと向き合うために必要な要素をしっかりと考えられているところに感動!!しました。 MAXHUBを使用して楽しく発表ができ、操作もすぐに覚えるところが今どきの学生なんだな~と感心しました。 ■そして3日目から授業です。 初日は、私が担当する基礎柔道整復学の授業でしたが、教科書をみて初めて見る専門用語に戸惑いを感じていました。 勉強するモチベーションを高めて欲しいと思い、『勉強をする必要性』についてグループワークを行いました。ここでも、感動!! 学生みんなが、「自分が患者さんを治療する上で必要であること」、「症状を鑑別するために必要なこと」、「責任がある仕事だから」、「より良い治療ができるようになるため」など、常に患者さんを中心に考えがあり、将来、自分が目指す職業やその理想をしっかり持った意見がたくさん出ました。 なぜ学ぶ必要があるのか?というその「本質」をしっかりと考えてもらうことで難しい勉強も乗り越えて欲しいと思っています。 授業の後は、高田馬場周辺の飲食店にお昼ご飯を食べに行ってくるねーなんて言いながら集団で帰っていきました。 高田馬場は、美味しいお店がたくさんあるんですよね。これも楽しみの一つですね。 ■ 次の日も感動!! 昨日の授業で、宿題とした課題を友達と一緒に勉強をしていました。 教科書を見ながらお互いに学び合いをしている姿に感動!! 質問があったので覗いてみると、なんと!教えていないところまで教科書を調べながら学習をしているではないか!!私は嬉しくてたまりませんでした。感動!! 入学後から感動!!の連発で、これからの3年間に期待がふくらみ、私自身も頑張ろうとモチベーションが上がりました。 ■新入生が感じていること 1.友達ができるかな? 2.実技が楽しみだから頑張ろう! 3.勉強頑張ろう! 4.専門用語が難しいから大丈夫かな? 5.朝寝坊しないで学校に行けるかな? 入学時の一番の悩みは、新しい友達と仲良く打ち解けることができるだろうか、友達ができないかも・・・・と不安を感じている人が多いです。 実際は、同じ目標に向かっている学生同士なので、すぐに仲良くなっている傾向があります。 でも、内気で積極的にみんなの輪に入れない学生もいると思います。 嫌われたらどうしよう、孤独になったらどうしようと考えて過ぎて、自信が持てない行動になったりしていませんか。 余計にその雰囲気が人を寄せ付けなくなっていることもあります。 嫌われたらどうしようと不安になる気持ちも分かります。 話しかける前に相手を探ったりしてしまうことをせずにできるだけ多くの人に話しかけるのが大事です。 人は第一印象が優先されるので、見た目もそうですが、相手が感じる雰囲気も大事になります。 ■お友達を作るための心理効果 心理学に「初頭効果と親近効果」というのがあります。 第1印象に関係するのが初頭効果です。 人間は、出会って数秒の間に相手の印象を決定する傾向があります。人は見た目で判断と言われますね。 最初に、怖い・気弱・話しかけづらいなどの印象を与えてしまうと、その印象が長い間残り続けてしまうのが初頭効果の影響です。 これは、勉強でも「何かを覚える」という時に初頭効果が影響することがあります。 勉強をしたい気持ちはあるが、最初に苦手と感じた場合積極的に取組むことができなくなります。 相手の印象を変えるのが親近効果です。 終わりや去り際の印象を与え、最初に得た印象から、その人のたくさんの情報を得ることで相手の印象が変わり最後に与えられた印象や情報が影響するのが親近効果です。 よくあるのが、最初は仲良くなれなかった友達も相手を知る時間が長ければ長いほど印象が変わり仲良くなっていくことがありますよね。 それが初頭効果と親近効果という関連の人の心理なのです。 入学するとまず初めに自己紹介があります。 みんなと打ち解けていないときの自己紹介は人物像の全体的なイメージが定着します。 この、初頭効果と親近効果を上手く使うことで関心度が高まります。 積極的になれない性格の人は、初頭効果を利用して話を工夫し、相手の関心を引くような話を冒頭に持ってきて第1印象がより引き立つようにアピールすると印象が良くなります。 そうすれば、クラスの仲間と打ち解ける時間は長くかからないと思います。 これからゼミなどに入り、先輩ともたくさんの交流があると思います。 最初のインパクトに左右されず相手の良いところをたくさん見つけて欲しいと思います。 春ですね。温かくなり身体を動かしやすい季節になりました。 4月から柔道の授業を担当することになり、自分の身体が動けるか心配でトレーニングをしています。 学生から、先生!本当に柔道ができるんですか?と言われます。 小学生から社会人まで本格的に柔道をしていたので特技と言えば柔道なのですが、学生からは“お母さん”という印象しかないらしいです。 授業でビシッと技を決めて、お姉さんと言われるように楽しく頑張りたいと思います。(笑(*^-^*)笑) 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 ]
-
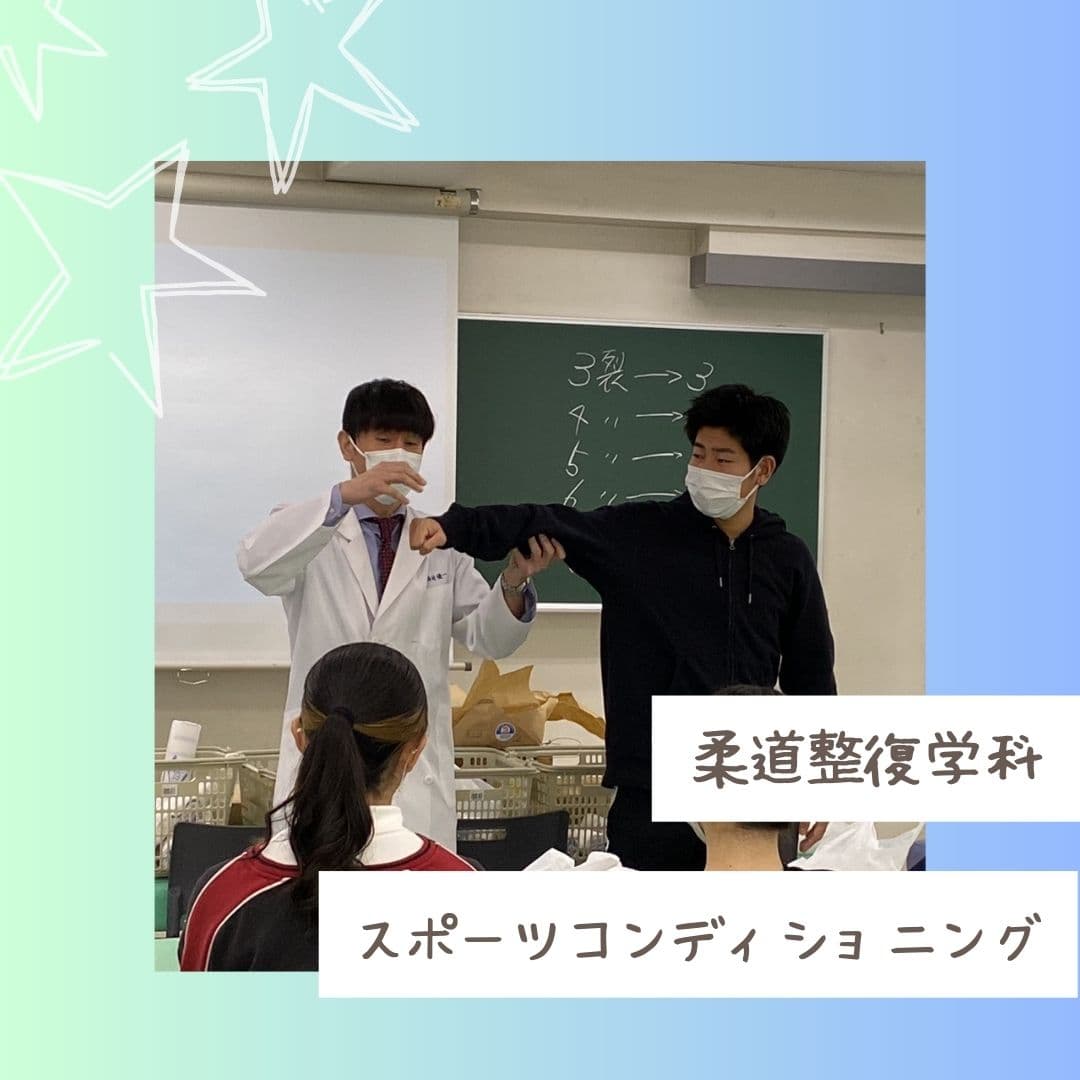 2023/04/06授業見学
2023/04/06授業見学- 【授業レポート】柔道整復学科:スポーツコンディショニング
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 入学式、オリエンテーションを経て、新1年生の授業が開始されました! 今回は、柔道整復学科 昼間部 1年生 スポーツコンディショニングの授業を取材しましたので、その様子をお届けします。 担当は柔道整復学科専任教員・西村先生です。 今回の授業は初回ということで、柔道整復師の資格やこれからの授業について丁寧に説明があった他に、柔道整復学科の学科長・森下先生と柔道整復学科の副学科長・青木先生の姿も。 勉強はもちろん大切ですが、学校生活も同時に大切にしてほしい。 その為のサポートを全力でしていきます!と熱いメッセージをいただきました。 スポーツコンディショニングの授業では、スポーツに関わる実践的な基礎知識を深めていきます。 プロのスポーツ現場で何をすれば良いのか、そして何をしてはいけないのか。 テーピングやストレッチ方法のメリットとデメリットをしっかり把握する、危機管理能力の高さが大切です。 来週は早速「足首のテーピング」の授業! その日に学んだことを次の日に現場で実践するような気持ちで頑張りましょう! お疲れ様でした!✨]
-
 2023/03/31コラム
2023/03/31コラム- 【片橋先生コラム・第35弾】腰痛になりました!
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第35弾をお届けします! 腰痛になりました! こんにちは、柔道整復学科専任教員の片橋です。 東京は桜が満開です🌸 さて、私は最近、腰痛になりまして・・・(笑) 1日は寝込みました。 腰痛にはあまりならないのですが、柔道整復師だって腰痛や肩こりになりますよ。 これはヒトの、二足歩行をするようになった人類の宿命ですね。 その時思ったのが、人によって腰が痛いの「腰」はさまざまだなーということ。 骨盤の上のウエストに該当する所が痛い人がいれば、もう少し上の背中が痛い人がいて、逆にもう少ししたのお尻の辺りが痛い人もいる。 骨盤については<<昨年夏のコラム>>を見てくださいね 骨盤はいくつかの骨が組み合わさった部分の呼び方で、左右の寛骨と仙骨と尾骨をまとめた言い方です。 仙腸関節 私の場合は、骨盤の関節で仙腸関節と言われるところが痛かった(´;ω;`) 寛骨と仙骨の間、骨と骨のつなぎ目のところです。 背骨の続きの仙骨が真ん中にあって、寛骨は右と左にあります。 ですから、仙腸関節は右と左があります。 私は左の仙腸関節が痛い腰痛でした。 関節が痛みの原因だったのですね。 腰痛の場所によっては、筋肉が痛かったり、神経が原因だったりもします。 いずれにしても、腰が痛くなるということはそこに負担がかかっていて、あなたに「休んでください」と言っているのですね。 今回、私は腰痛になるまで仙腸関節に負担をかけてしまいました。 次は痛みとして仙腸関節が悲鳴を上げる前に労わってあげたいと思います。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員)]
-
 2023/03/24その他
2023/03/24その他- 【山中先生コラム・第10弾】~顔のくすみや歪み~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第10弾! 顔のくすみや歪み マスク生活が緩和されました。 顔のたるみや、くすみ気になりませんか? そんな方におすすめポイントをお伝えします。 『翳風(えいふう)』 耳たぶの裏側にあるくぼみにあります。 片方だけかたくなっていたり、両側が硬くなっている場合は優しくほぐして見てください。 顔や顎(アゴ)の歪み、血色が良くなってきますよ。 毎日のセルフケアにオススメですので、是非ためしてみてください。 皆さんの日常に取り入れてもらえたら嬉しいです。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
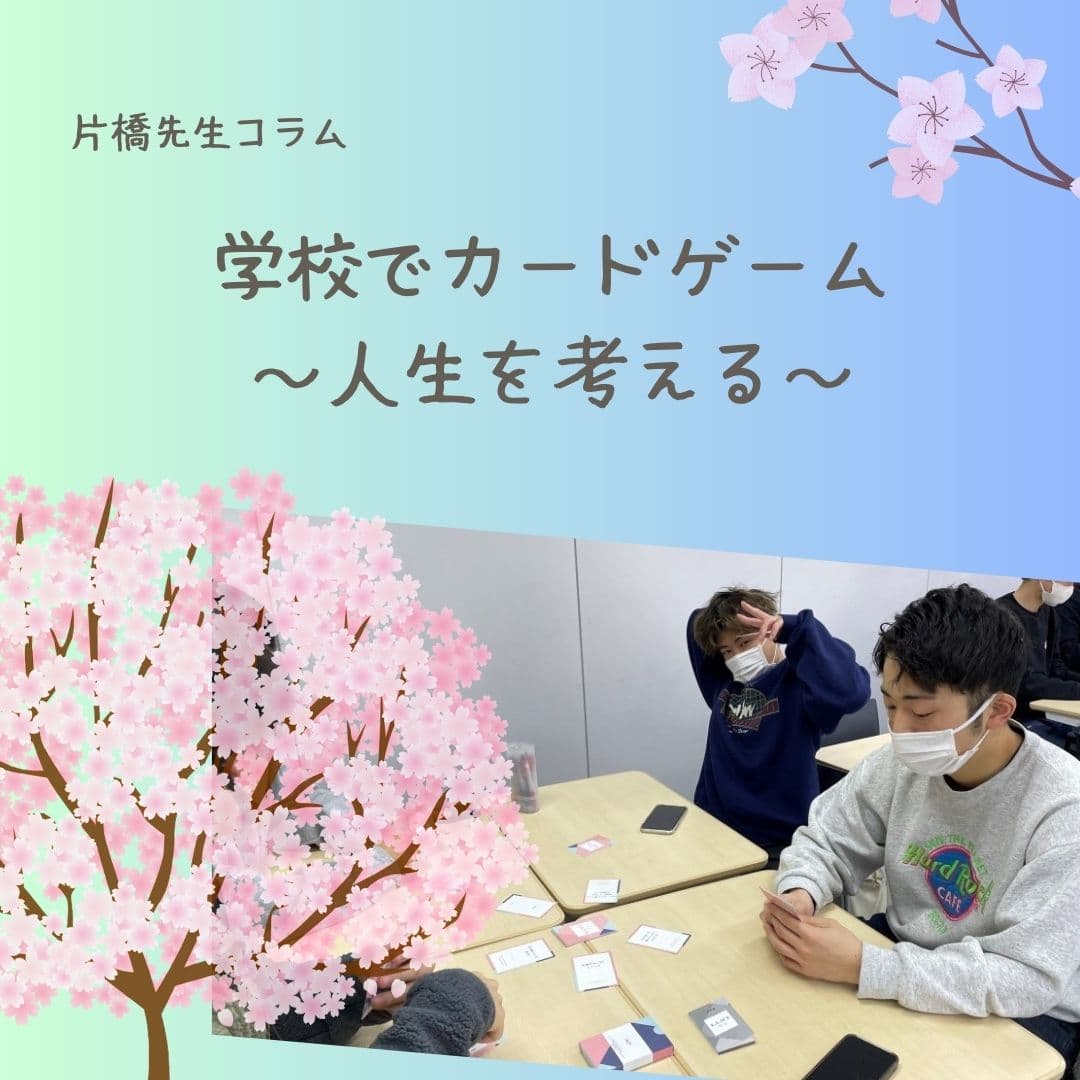 2023/03/22その他
2023/03/22その他- 【片橋先生コラム・第34弾】学校でカードゲーム~人生を考える~
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第34弾をお届けします! 学校でカードゲーム~人生を考える~ 今日のタイトル、気になりましたよね? なんと、授業でカードゲームが登場しました!! 題して「もしバナゲーム」! もしバナゲーム ご存知の方はいらっしゃいますか? みなさんが、例えばあと3か月しか生きられない、と設定して、どのような最期を迎えたいのか、希望する内容のカードを集めるゲームです 亡くなる前の、個人的な整理や遺言などを行う終活とは違います。 あくまでゲームですが、どのような状態で最後を迎えたいのか、身体的、心理的、肉体的に、最後に望む環境は何なのか、チーム内で自分に必要なカードを選びます。 カードの枚数は5枚。1枚捨てて1枚選びます 「え~」 「○○だな」 「これはいらない」 わいわいブツブツ声に出したり、じっと考え込んだり、ゲームといえども真剣に選んでいましたよ。 チームやクラスによって、または年齢層によって、選ぶカードが全然違いました。 【親友が近くにいる】 【家族に迷惑をかけない】 【医療機器につながれていない】 【ユーモアがある】などなど みなさんなら、どれを選びますか? カードを全部開いて、交換するものがなくなったらおわり。 集めたカードを優先順位で並べてスマホでパチリ!写真に残します。 最後に、集めたカードの中で優先順位が高いものについてチーム内で、なぜそれを選んだのかを理由をつけて発表しました。 仲の良いチーム内での発表は、友達の新たな面を発見するとともに、その人が最後に望むことを知ることになります。 海外発祥のこのゲーム、医師が作った日本版は介護現場の研修で大人気とのこと。 救急救命士としても活躍されてきた講師の授業での、もしバナゲーム。 介護や救急の現場は死と向き合わなければならないことがあります。 その時は、急に来ます。 いざというときに自分はどうしてほしいのか、大切な人に知らせておくことは自分の望む最後を迎えるうえでとても意義のあること。 私も家族とやってみたくなりました。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
 2023/03/03コラム
2023/03/03コラム- 【山中先生コラム・第9弾】~花粉症~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第9弾! 花粉症 皆さんは、花粉症の症状でていませんか? 目の痒みや、鼻水、肌が痒くなったりと様々な症状が出るのが特徴です。 では、どう対処したら良いかオススメのツボをご紹介致します。 1、目の痒みには 『合谷(ごうこく)』『欑竹(さんちく)』がオススメです。 合谷は、以前お話ししましたので今回は「欑竹(さんちく)」をご紹介します。 眉毛の内側にあるくぼみを探してみてください。 合谷と一緒に押してもらえると、目の痒みに効果的です。 2、鼻水には 『上星(じょうせい)』がオススメです。 鼻のラインで、髪の毛の生え際から親指一本分入った所にあります。 生え際から頭のてっぺんに向けて押してみてください。 上記のツボで、花粉対策をしていきましょう。 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
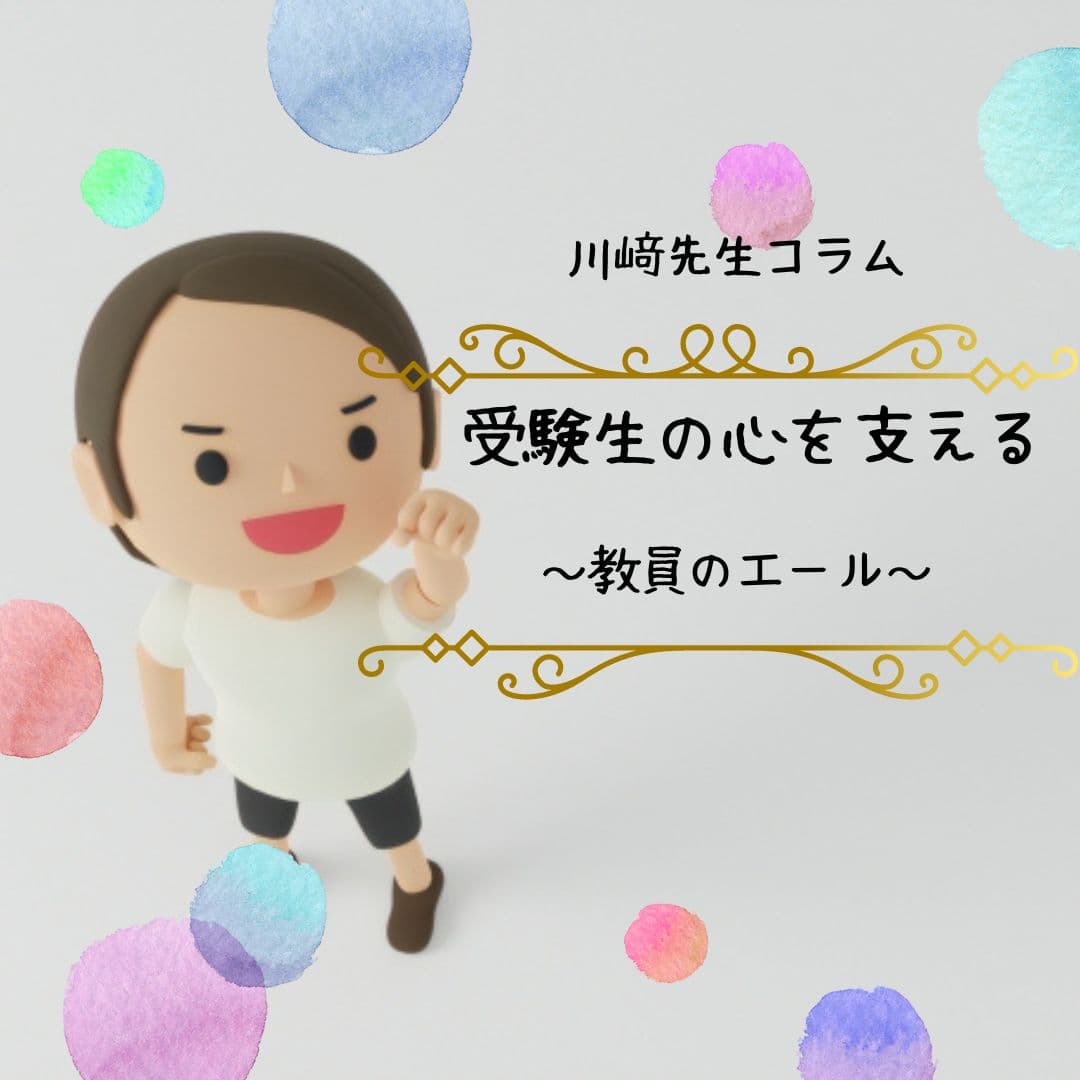 2023/02/24コラム
2023/02/24コラム- 川﨑先生コラム 第34弾「 受験生の心を支える~教員のエール~」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第34弾をお届けいたします! 受験生の心を支える~教員のエール~ 国家試験目前になりました。 はり師・きゅう師の国家試験は2月26日(日)、柔道整復師の国家試験は3月5日(日)に実施されます。 本校の3年生は、ラストスパートをかけて自分の将来の夢を実現するために頑張っています。 見守る私たちは、ご飯を食べているか?体調を崩していないか?思い悩んでいないか?とても心配になります。 学生は合格まで気が抜けず、精神的にも大きな負担がかかりたくさんの勉強をしても不安で仕方がないでしょう。 それでも一生懸命立ち向かい努力している姿はたくましく誇りに思います。 私たちができることは、学習サポートと温かい言葉をかけてあげることにより心の負担を少しでも軽くしてあげることです。 しかし、声をかけるにしてもポジティブ過ぎても負担になるためとても配慮が必要です。 受験生の心中 1位は、もっと早くから勉強をすればよかったー( ;∀;)! 2位は、どこまで勉強すれば不安が解消されるのだろうか。 3位は、最後まであきらめずに頑張ることができるだろうか。 4位は、頑張っているけど結果が見えない。 5位は、3年間頑張ったからきっと大丈夫。合格するよ。 学生が国家試験前に思っていることは毎年ほぼ同じで変わりません。 時間に対しての後悔、勉強しても自信が持てない、モチベーションの維持に関することが多いです。 国家試験の勉強量は多く、時間をかけてコツコツと努力するしかありません。 やらなかった時に感じる後悔は、時間が経過するにつれて増大していく傾向があります。 それが心の負担に繋がってしまいます。 「努力は無限」です。 スタートが異なっても、コツコツ諦めないでやり抜けば☆逆転必勝☆もあります。 夢を力にかえて強い気持ちで成し遂げて欲しいと思います。 そういえば、2年生がこんな話をしていました。 3年生が、『早いうちから勉強した方がいいよ。自分は後悔しているから。』と言っていたよ。『だからそろそろ国試に向けて少しずつやらないとダメだよね。』 先輩から後輩へ、現実と向き合った結果の言葉をどう受け止めてくれているかわかりませんが、やらないといけない意識が出たことは良かったと思います。 先輩の努力しているカッコいい姿を見て、何事も「後悔先に立たず」ということがないように早めに学習習慣を身に着けてほしいです。 受験生にかける言葉 応援の言葉をかけたいけどプレッシャーになる言葉は控えたいですね。 まずは、日々の努力を誉めてあげることが大切です。 褒められることで認めてもらっていると感じ、奮起してくれる傾向があります。 そして頑張った自分に対しても自分で自分を褒めるようになり、心が満たされてモチベーションが上がっていきます。 NGとなる言葉は、自分の経験を押し付けるような話や、否定的な言葉です。 焦りと不安から自分はダメなのだと思ってしまいます。 また、必死に頑張っている状況に頑張れ!とか疲れている時にやる気出せー!もっと頑張れー!と言われると、これ以上頑張れないっていうほど頑張っているのに、これ以上何を頑張ればいいの?と思ってしまい、精神的に追い詰めてしまいます。 いつも自分を見てくれて頑張りを認めてくれていると思う言葉、緊張をほぐすような言葉を選び、信じて温かく見守ってあげることが大切です。 1年生・2年生のうちに身に着けること 1年生・2年生では学習習慣を身に着けることが大切です。 具体的に言うと「自己学習力」をつけることが最も大切です。 勉強をしない、または苦手という学生のほとんどは、学習計画が立てられず、自分が何から勉強すればいいのかも考えられていません。 また、勉強しているのに成績が伸びない人も学習計画が立てられていません。 勉強がうまくいく秘訣は、しっかりした学習計画を立てることです。 今日やるべき事は今日済ませる。という習慣がついている人と、明日以降やれば良いと思ってしまう人とでは、受験当日までの勉強量に大差がつきます。 自己学習のための計画を立てる 計画を立てる場合、 ①まず勉強する科目を書き出し、科目に費やす時間や何をするべきかを考えます。 ②一覧にしたら優先順位をつけていきます。 ③1週間の中に振り分けていきます。毎日、同じ時間帯に勉強をするように計画を立てるほうがルーティン化できて勉強の習慣を身に着けることができます。 勉強に慣れていない人は、30分~45分程度の時間で区切り少しずつ増やしていくのも良いでしょう。 1週間の計画が実行できるようになったら学習範囲を広げて月ごとの計画を考えてみてください。 また、自分の学習方法はどのような方法が向いているのかを性格も踏まえて考えてみると効率の良い勉強ができるようになっていきます。 学習計画に沿って勉強するうえで特に大変なことは、計画を無視して楽しいことや好きなことをやりたい誘惑にかられることです。 自制心が必要となりますが、常に最善を尽くし、目の前の課題に集中してください。 もちろん、勉強を継続するために自分の時間も大切にしてバランスよく両立してくださいね。 自己学習力は就職しても役立つ 臨床で重要視しているものは、利他の心、倫理観、コミュニケーション力など相手を敬い、信頼関係を築き、道理やルールを守りながら仕事ができる人です。 その他に、自己研鑽力が身についているかどうかも重要とされます。 自己研鑽とは、自分自身を鍛えて、学問や仕事などの特定の分野の技術を向上したり、知識を深めたりすることです。 能力を上げることが自己研鑽です。 これは、計画性や自己学習力が身に付いていないとできません。 国家試験が終われば、次は有資格者として臨床現場に立ちます。 患者様の気持ちを汲み取り一人一人に合わせたオーダーメイドの治療を考えていく必要があります。 新人であるほど柔軟な対応をして自己研鑽に励むことで経験値が上がり、仕事を任される範囲が広くなります。 そして他者からの評価を得ることができるでしょう。 終わりに 受験を控えている学生にとって精神的なサポートが何よりも必要です。 周囲の励ましの一言が、心に深く響き勇気を出すことができます。 受験生の皆さん、努力が合格につながっています。今を大切にして頑張って欲しいと思います。 私は、見守ることしかできない日本医専のお母さんですが、学生の皆さんの3年間の成長は素晴らしく皆さんの努力も知っています。 残り少ない日々を諦めないで乗り越えてください。 そして何をするにも体が資本です。 健康であることも合格につながる秘訣です。 体調管理をしっかり考えていきましょう。 本校では、国試直前三禅問合宿を行っています。 朝6時半からランニングをして体と心を整えて、朝から夜まで勉強します。 勉強は辛いけど励まし合いながら参加しているそうです。 禅とは精神統一を表す意味があります。座禅のイメージで表すとわかりやすいですね。 もう一つは実体験をして体得する。という意味があります。 真実を体得するということになります。 そして三禅は、四禅の一つ前で「離喜妙楽」とも呼ばれ、楽と一境性が残る状態です。 心の浮動・後悔・落ち着きのない状態を排除し、心配事もなく集中し安らかになる状態を表します。 三禅問合宿は、心を落ち着かせて集中し課題を克服することで安らぎを得る。 つまり合格へ導くという気持ちが込められた合宿です。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
 2023/02/17コラム
2023/02/17コラム- 【片橋先生コラム・第33弾】~肩がハズレそう⁈~
-
日本医学柔整鍼灸専門学校です。 今回は片橋先生によるコラム・第33弾をお届けします! 肩がハズレそう⁈ 寒波がきていましたが、お元気でしたか? そろそろ春の暖かさを感じたいですね。 日本医専は今年度の期末試験の追い込みから試験が終わって、春休みが楽しみな頃です。 3年生は国家試験目前にがんばっていますよ。 さて、普段の生活で肩がはずれそうになったって聞いたことはありますか? 朝起床時に伸びをしたら肩が抜けそうになった、水泳をしてして肩が一瞬外れた、リュックを背負おうとしたら肩がガクッとなった、など結構あるんですよね。 抜けそうになった、一瞬外れた、というのは骨の一部がずれてすぐに元に戻ったということで亜脱臼が考えられます。 関節が完全にはずれるつまり、骨と骨のつながりがズレて重なる部分が全くなくなったものでこれを完全脱臼といいます。 それに対して骨と骨のつながりが一部ズレて重なる部分と重ならない部分があるものを不全脱臼または亜脱臼といいます。 肩関節が完全にハズレると自分の力で元に戻すのはなかなか難しいです。 でも、亜脱臼だと骨が重なっている部分があるため自分の力で戻せることが多いのです。 だからといって、みんながみんな日常生活で肩がハズレるわけではありません。 外れやすい体の人がいるのですね。 それをルースショルダーといいます。 若い女性に多くてクラスに一人くらいはいますよ。 今年も授業をしていて「あ、私のことだー!」とか「バタフライをしていて肩が外れました」とか学生さんから話がありました。 異常なものではなく原因もわからないルースショルダー。 肩がちょっとゆるい人なんですね。 腕を振りかぶる動作で外れやすいので、この動作はしないように気をつけましょう。 (監修/片橋るみ先生:柔道整復師 介護支援専門員) 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
 2023/02/10コラム
2023/02/10コラム- 【山中先生コラム・第8弾】~メンタルケア~
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 山中先生によるコラム・第8弾! メンタルケア 皆さんは、やる気になれない時、気持ちに乱れがある時どのように対処していますでしょうか? お風呂に入る、好きな曲を聴く、好きなものを食べる… 皆さんが、それぞれ行っている事に今からお伝えする物を一つ付け加えてみてください。 「内関(ないかん)穴」 メンタルケアには持ってこいの、素晴らしい施術ポイントです。 不安に感じることや、気持ちを落ち着けたい時に使ってみてください。 その他、酔い止めに使用したり、血圧の高い場合に用いたりとさまざまな場面で使用することができますよ。 場所は、手首の内側(曲げた時にできる一番深いシワ)から指3本分で、骨と骨の間にあります。 是非試してみてください。 <<YOUTUBEでも詳しく解説しています!>> 担当教員:山中 直樹先生(本校柔道整復学科 専任教員) 鍼灸師・柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 整膚師師範 山中先生は本校TikTokでも活躍中✨ <<定期的に開催されるペヤングチャレンジの様子はこちら>> 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
-
 2023/02/03コラム
2023/02/03コラム- 川﨑先生コラム 第33弾「筋肉をつけて冷え知らずになろう!」
-
こんにちは! 日本医学柔整鍼灸専門学校 広報担当です。 川﨑先生コラムの第33弾をお届けいたします! 筋肉をつけて冷え知らずになろう! 最近、寒さが厳しくなりましたね。 平年の気温は1月初めから少しずつ低下し下旬から2月初めにかけて、1年で最も寒い時期で大寒といわれる時期です。 冷え性で悩む人の多くは「手足の冷えが」最も多いです。 冷え性や寒さが苦手な人は運動を余りせず筋肉量が少ないことが問題です。 足が冷えるからと、夜寝るときに靴下をはいて寝ている人も多いと思いますが、靴下をはいて寝ると汗をかいてその汗が原因で足が冷えて逆効果になっていることもあります。 筋肉を味方に付けて冷え知らずになりませんか。 冬の脂肪は体を冷やす 血液はエネルギー代謝によって生まれた熱を全身に運ぶ役割があります。 冬は血管が収縮するため代謝が低下し冷えやすくなります。 特に、手足の血管は細いので温まりにくく冷えやすいといえます。 脂肪は外気温に影響されやすく気温が下がると、脂肪は血管が少ないため内側から温めることができなくなります。 男性よりも女性の方が、皮下脂肪の量が多いため冷え性の人が多いです。 また、内臓が冷えると基礎代謝が落ちて痩せにくくなり、免疫力も低下して風邪をひきやすくなる、便秘など様々なデメリットがあります。 一方、筋肉は熱を生み出し血管が多く集まっているので熱を維持・産生することができます。 そのため、運動によって脂肪を落として筋肉をつけることは冷えの解消に繋がり、代謝をあげて痩せやすい身体になります。 筋肉にはどのような働きがあるのか 筋肉量は年齢と共に、少しずつ低下していきます。 30歳から低下が始まると言われています。 だから、持続的に運動をすることが必要なのです。 筋肉は、身体を動かす働きだけではありません。以下のような働きを担っています。 ①姿勢やバランスを保持する。 ②血管が収縮し、血液を心臓へ戻す。 ③エネルギーを産生して熱をつくり代謝を上げる。 ④血管、神経、内臓などを外部の衝撃から守る。 ⑤からだ全体の約6割の水分を保持する。 ⑥免疫力を上げる。 ⑦生理活性物質を分泌する。 運動により筋肉から放出される生理活性物質(マイオカイン)の分泌を促進すると、代謝の促進による脂肪肝改善・体脂肪分解、認知症の予防、骨形成促進、動脈硬化予防、免疫能改善、抗炎症作用などがあるとされています。 また、運動することにより脳の循環が良くなり神経細胞の活動性が向上し脳パフォーマンスも向上すると言われています。 筋力低下が認知機能の低下や抑うつのリスクも高めることもわかっています。 筋肉をつけることは、冷え予防だけでなく身体機能の活性化につながり健康寿命にも繋がっています。 人はマッスルメモリー(筋肉の記憶力)がある!? 以前にトレーニングをしていた人は、遺伝子がそのトレーニングや負荷を記憶していると言われています。 歳をとってからトレーニングする際も、マッスルメモリーが残っていれば効果的にトレーニングができます。 筋細胞はほかの細胞よりも大きく、多くの細胞核が含まれていて、この核のおかげで筋肉は肥大し、筋肉トレーニングで増殖した核はトレーニングを中断しても長期間消失せずに残ると考えられています。 だからトレーニングを再開すると身体が反応し、以前の筋肉量まで取り戻すことができるのです。 特に、部活動や身体発達のピークに運動をしていた人ほどマッスルメモリーが残りやすいため、短期間でトレーニングの効果がでると言われています。 効果が出るまでの期間は、身体の細胞は約3カ月かけて入れ替わるので、3カ月以上継続する必要があります。 ただし、心肺機能は衰えると取り戻すことは難しく時間がかかります。 いきなり強い負荷の運動よりもウォーキングなどの軽い運動から始めて徐々に取り戻していくようにして下さい。 終わりに 筋肉がいかに大切であることは伝わったかと思います。 筋肉を動かさないと血行が悪くなり、冷えを助長することにつながります。 適度な運動で筋肉量の低下を防ぐことが重要です。 自宅で気軽にできる、腹筋やスクワットをやってみましょう。 日常の予防としては、太い動脈が皮膚のすぐ下を通っているところの、3つの首(首・手首・足首)を隠して体温を逃さないようにしましょう。 ストレスが原因で自律神経のバランスが乱れて冷え性に繋がっている人は、交感神経が優位になっているため、末梢血管の血行が悪くなり、手や足先が冷えやすくなりがちです。 心身の緊張を解きほぐすリラックスの時間を意識的に作るようにして下さい。 筋肉トレーニングよりも入浴やストレッチが効果的です。 冷えるからたくさん着込むのではなく、身体の根本から改善していくように心がけてくださいね。 時間があると、軽く運動をするように心がけています。 しかし、腸脛靱帯炎が発症してから治ったり再発したりを繰返して思うように運動ができません。 ひどいと膝がガクッと力が抜けて膝くずれが起きて歩くだけで痛みがあり悩んでいます。頻繁に治療院にも行けず、セルフケアーでストレッチローラーを使ってケアをしていましたが、一時的には良くなりますがなかなか改善しないです。 ある日、本校の先生からHypervoltという筋膜リリース機器を教えてもらいました。 偶然、先生が持っていたのでお試しさせて頂き、なんと5分程度の時間で痛みが改善したのです。 多くのトレーナーやアスリートが使用しているそうで、私も購入して大殿筋や腸脛靱帯をアプローチしてみました。 使用してからは、痛みが持続的に続くことがなくなりました。 手技に勝るものはないですが、セルフケアーを考えるとこういった機器に頼ることも必要ですね。 頑張って運動を続けたいと思います。 柔道整復師・鍼灸師 本校柔道整復学科 専任教員 川﨑有子 週末のイベントでは先生ともお話しができます! >>オープンキャンパス情報はこちら 先生のコラムや授業の様子がわかる! >>ほかの柔道整復学科ブログはこちら まずは日本医専を知ろう! >>資料請求はこちら]
- お問い合わせ
- info@nihonisen.ac.jp
- 03-3208-7741 平日 9:00 - 21:30
- LINEで問い合わせる







