柔道整復師について
柔道整復師と理学療法士、どっちがいい?違い・難しさ・年収をわかりやすく解説
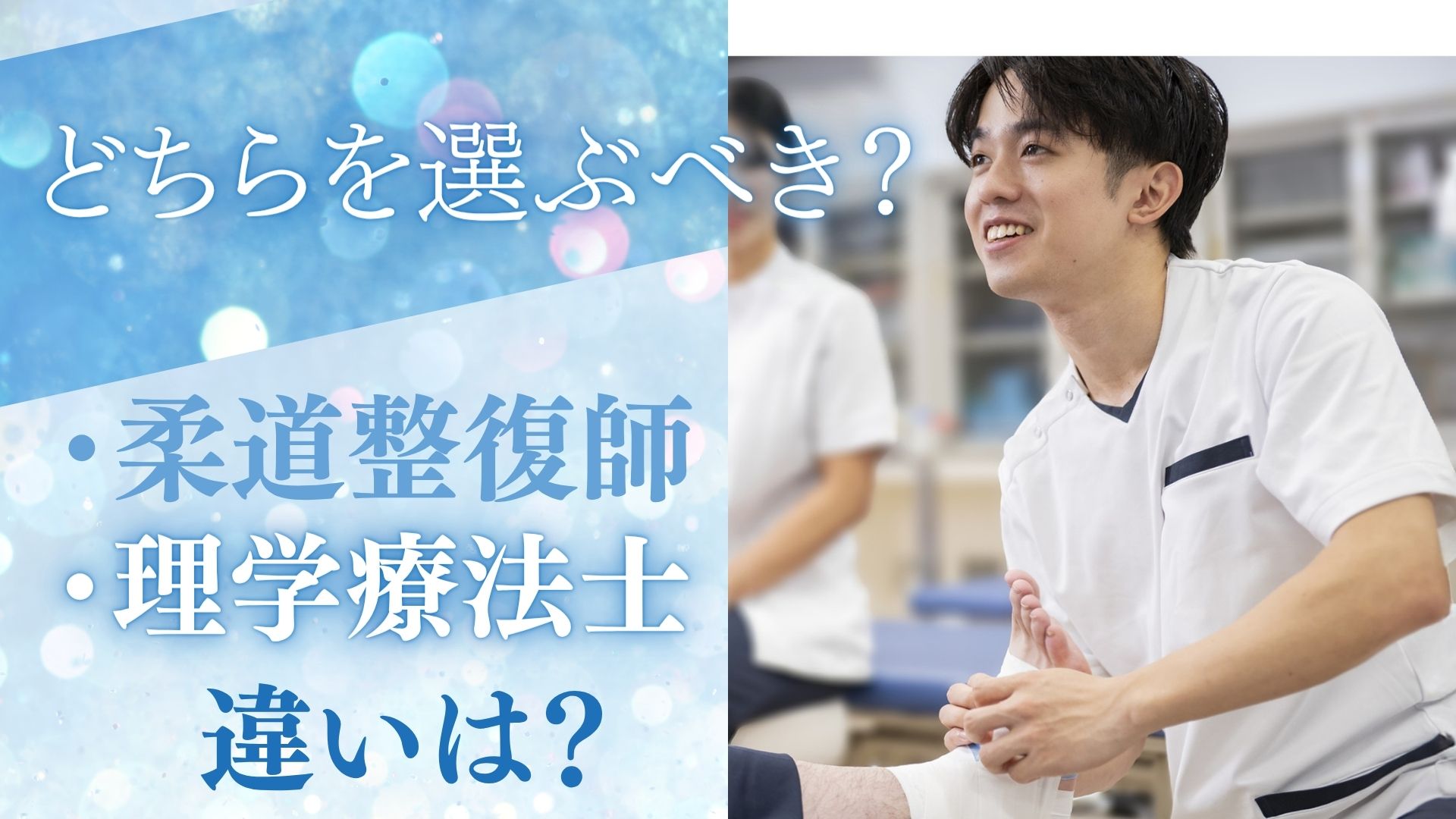
柔道整復師と理学療法士、どちらを選ぶべき?違いや年収、難易度を解説
柔道整復師と理学療法士は、どちらも身体の不調を改善する医療専門職ですが、その業務内容や活躍の場、資格取得の難易度には違いがあります。それぞれの専門性や仕事内容、働きがい、収入、適性について理解し、自身のキャリアプランに合った選択をしましょう。
柔道整復師と理学療法士の基本的な違い
柔道整復師と理学療法士の違いは、主に業務範囲と患者へのアプローチ方法にあります。
柔道整復師は「急性期の外傷」に特化しており、骨折や脱臼、捻挫などの処置を行うのに対し、理学療法士は「身体機能の回復」を目指し、運動療法や物理療法を通じてリハビリテーションを実施します。
このように、柔道整復師と理学療法士の違いは専門とする分野が明確に分かれているのが特徴です。
業務範囲と役割の比較
柔道整復師は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった急性期の外傷に対して、手術をしない「非観血的療法」を用いて施術を行います。これには、整復法による骨折や脱臼の徒手整復、固定法による患部の固定などが含まれ、応急処置として医師の同意なしで脱臼や骨折の処置が可能です。一方、理学療法士は、病気や怪我、高齢などによって身体機能が低下した人々に対し、運動療法や物理療法を用いて、身体機能の回復や維持を図る専門家です。その役割は、身体の構造や機能の専門知識に基づき、患者さんの状態を評価し、個別のリハビリテーションプログラムを立案・実施することで、日常生活動作(ADL)の改善や社会参加の促進を目指すものです。このように、柔道整復師は主に外傷の急性期対応にあり、理学療法士は機能回復のリハビリテーションにあると言えるでしょう。
柔道整復師の主な仕事内容
柔道整復師の主な仕事内容は、骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷といった急性期の外傷に対する施術です。具体的には、骨折や脱臼を元の位置に戻す「整復」、ギプスや包帯を用いて患部を固定する「固定」、そして症状の回復を促す「後療法」の3つの手技が中心となります。後療法には、手技によるマッサージやストレッチ、運動療法、物理療法などが含まれ、患者さんの自然治癒力を最大限に引き出すことを目的としています。また、痛みの軽減や機能回復のための指導も行い、患者さんが日常生活に早く復帰できるようサポートします。
柔道整復師と理学療法士は、対象とする疾患や治療のアプローチに違いがあります。柔道整復師は、骨折や脱臼、捻挫などの外傷に対する非観血的療法(手術をしない治療法)を行う専門職です。一方、理学療法士は、病気やケガ、加齢などにより身体機能に障害がある人に対し、運動療法や物理療法を用いて、基本的な動作能力の回復や維持、悪化の予防を図るリハビリテーションを専門としています。柔道整復師は外傷の応急処置とその後の機能回復に重点を置く一方で、理学療法士はより幅広い疾患に対応し、患者の生活の質を向上させることを目指します。
理学療法士の主な仕事内容
理学療法士の主な仕事内容は、病気や怪我、高齢、障がいなどによって運動機能が低下した人々に対し、身体機能の回復や維持、悪化の予防を目的としたリハビリテーションを提供することです。具体的には、患者さんの運動能力や身体状況を評価し、それに基づいて個別の運動プログラムを作成・指導します。これには、筋力トレーニング、関節可動域訓練、バランス訓練、歩行訓練などが含まれ、患者さんの状態に合わせて様々な運動療法を行います。また、温熱療法、電気療法、牽引療法などの物理療法も用い、痛みの緩和や血行促進などを図ります。さらに、日常生活動作(ADL)の指導や、福祉用具の選定・使用方法のアドバイスも行い、患者さんが自宅や社会で自立した生活を送れるよう包括的に支援します。理学療法士と柔道整復師は、対象とする疾患や治療のアプローチが異なり、理学療法士は広範な身体機能の回復と維持に焦点を当てています。
働きがいと患者さんとの関わり
柔道整復師と理学療法士は、どちらも患者さんの身体的な不調を改善し、社会復帰を支援する点で共通の働きを持ちますが、その関わり方にはそれぞれの専門性に応じた特徴があります。
柔道整復師の働きがい
柔道整復師の働きがいは、患者さんの痛みを和らげ、外傷からの回復を直接的に支援できる点にあります。
骨折や脱臼など、突然の怪我で苦しむ患者さんが来院し、適切な処置によって症状が改善していく過程を間近で見られることは、大きなやりがいとなります。
特に、スポーツ外傷を負ったアスリートの復帰をサポートする場面では、スポーツトレーナーとしての側面も持ち合わせ、患者さんの目標達成に貢献できる喜びを感じられます。
患者さん一人ひとりの症状に合わせた施術を行い、感謝の言葉をもらうことも、柔道整復師としてのモチベーションを高める要因となるでしょう。
地域に根差した接骨院や整骨院で働くことが多いため、患者さんとの距離が近く、継続的な関わりの中で信頼関係を築けることも、柔道整復師の働きがいにつながります。
理学療法士の働きがい
理学療法士の働きがいは、患者さんの身体機能が回復し、できなかったことができるようになる過程を間近で支援できる点にあります。
例えば、事故や病気で歩行が困難になった患者さんが、リハビリテーションを重ねて再び自分の足で歩けるようになる姿を見た時、大きな達成感と喜びを感じることができます。
患者さんが諦めずにリハビリに取り組む姿に寄り添い、小さな変化や進歩を共に喜び合うことで、患者さんの生活の質の向上に貢献できることに大きなやりがいを見出すでしょう。
高齢者の転倒予防や、障がいを持つ方の社会参加を支援するなど、患者さんの人生をより豊かにする手助けができることも、理学療法士の大きな魅力です。
患者さんからの感謝の言葉や、生き生きとした表情を見ることが、日々の業務へのモチベーションにつながります。
勤務先と給与水準
柔道整復師と理学療法士は、それぞれ異なる勤務先で活躍しており、それに伴い給与水準にも違いが見られます。
柔道整復師の主な勤務先は接骨院や整骨院であり、開業することも可能です。年収は勤務先や経験、能力によって幅がありますが、一般的に平均年収は約430万円から460万円程度とされています。
一方、理学療法士は病院やクリニック、介護老人保健施設、訪問看護ステーションなど多岐にわたる医療・介護施設で活躍しており、平均年収は約364万円から432万円程度とされています。
これは、柔道整復師が独立開業によって高収入を得る可能性や、勤務先によってはスキルや経験に応じて昇給が期待できるためと考えられます。
ただし、どちらの資格も経験を積んだり、専門性を高めたりすることで、年収アップを目指すことができます。
柔道整復師と理学療法士の適性
柔道整復師と理学療法士、どちらの資格を目指すにしても共通して求められる資質がありますが、それぞれの専門性や仕事内容から適性が分かれるポイントも存在します。
自身の性格や興味、将来の目標などを考慮し、どちらの道がより自分に合っているのかを見極めることが重要です。
共通して求められる資質
柔道整復師と理学療法士は、専門分野は異なりますが、患者さんと向き合う医療専門職として共通して求められる資質がいくつかあります。
まず、患者さんの身体の不調を改善し、社会復帰を支援する仕事であるため、人を助けたいという奉仕の精神と、相手の痛みに寄り添える共感力が不可欠です。
次に、患者さんの状態を正確に把握し、適切な処置やリハビリテーションを行うためには、論理的な思考力と観察力が求められます。
さらに、患者さんとの信頼関係を築き、治療計画を共に進めていくためには、良好なコミュニケーション能力が重要です。
説明を分かりやすく伝える能力はもちろん、患者さんの話に耳を傾け、不安や悩みを引き出す傾聴力も大切になります。
また、柔道整復師と理学療法士のどちらも、日々進歩する医療知識や技術を学び続ける向上心と、困難な状況でも諦めずに患者さんをサポートする忍耐力も求められるでしょう。
柔道整復師に向いている人
柔道整復師に向いている人は、まず「骨折や脱臼、捻挫といった急性期の外傷に興味があり、それらを徒手で治療することに魅力を感じる人」が挙げられます。
また、患者さんの痛みをいち早く取り除き、その場で効果を実感できる治療にやりがいを感じる人にも適しているでしょう。
スポーツ外傷に特化して学びたい、将来的にスポーツトレーナーとして活躍したいという明確な目標がある人にとっても、柔道整復師の資格は大きな強みとなります。
患者さんとの距離が近く、日々のコミュニケーションを通じて信頼関係を築きたいと考える人や、将来的には独立開業を目指したいという意欲のある人にも適していると言えるでしょう。
手技による治療に興味があり、実践的なスキルを磨きたいという探求心を持つ人も、柔道整復師として活躍できる可能性を秘めています。
理学療法士に向いている人
理学療法士に向いている人は、長期的な視点で患者さんの機能回復をサポートすることにやりがいを感じる人です。
病気や事故で身体機能が低下した方が、少しずつリハビリを重ねて日常生活を取り戻していく過程に寄り添い、その変化を共に喜び合える共感力と忍耐力がある人に向いています。
また、身体の構造や運動メカニズムに深く興味があり、科学的根拠に基づいたアプローチで患者さんを治療したいと考える知的好奇心旺盛な人にも適しています。
理学療法士は、医師や看護師、作業療法士といった多職種と連携して治療を進めるため、チーム医療の中で積極的に意見を交わし、協調性を持って取り組める能力も求められます。
論理的な思考力と分析力を用いて、患者さん一人ひとりに最適なリハビリテーションプログラムを立案・実行できる人も、理学療法士として活躍できるでしょう。
資格取得までの道のり
柔道整復師と理学療法士、どちらの国家資格も取得するためには、専門の養成施設での学習と国家試験の合格が必要です。
両資格ともに専門知識と技術が求められるため、一定の難易度があります。
しかし、それぞれの試験内容や学習期間、そして進路によって難しさは異なります。
国家資格の概要
柔道整復師と理学療法士は、ともに厚生労働大臣が認定する国家資格です。これらの資格を取得するためには、国が定めた養成施設で所定の課程を修了し、国家試験に合格する必要があります。養成施設には、大学と専門学校があり、どちらの選択肢も国家試験の受験資格を得ることができます。大学は4年制が一般的で、専門学校には3年制と4年制があります。柔道整復師と理学療法士の国家試験は年に一度実施され、合格することでそれぞれの資格が与えられます。医療行為を行うための重要な資格であるため、その取得には専門性の高い知識と技術の習得が求められます。
柔道整復師の国家試験と難易度
柔道整復師の国家試験は、例年3月に実施され、筆記試験形式で行われます。
試験科目は、解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論、関係法規など多岐にわたります。
これらの科目を網羅的に学習する必要があり、特に柔道整復理論や臨床に関する知識が重要視されます。
合格率は、近年では約60%前後で推移しており、2025年の合格率は57.8%でした。
2023年には50%を下回ったこともあり、決して易しい試験ではありませんが、 しっかりと対策を立てれば十分に合格を目指せる難易度と言えるでしょう。
しかし、専門的な知識の習得に加え、実技試験が廃止されたとはいえ、柔道整復師の業務は手技を伴うため、養成施設での実習を通じて実践的な技術を身につけることが不可欠です。
国家試験の難しさだけでなく、臨床現場で役立つ知識と技術の習得が求められます。
理学療法士の国家試験と難易度
理学療法士の国家試験は、例年2月下旬に実施される筆記試験です。
試験科目は、解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学、人間発達学、理学療法概論、理学療法評価学、治療理学療法学、義肢装具学、地域理学療法学、理学療法管理学、関係法規など、広範な知識が問われます。
特に、運動学や生理学、治療に関する専門知識の理解が重要です。
合格率は例年80%台と比較的高い水準で推移しており、柔道整復師の国家試験と比較すると、やや合格しやすい難易度とされています。
しかし、これはあくまで平均値であり、出題範囲の広さと深い専門知識が求められるため、油断はできません。
養成施設での学習はもちろんのこと、国家試験対策を計画的に進めることが、合格への鍵となります。
専門養成施設の課程
柔道整復師の国家試験受験資格は、文部科学大臣が指定した学校または都道府県知事が認可した養成施設で3年以上の修業が必要です。
一方、理学療法士の国家試験受験資格は、厚生労働大臣が指定する養成施設で3年以上(4年以上が一般的)の課程を修了する必要があります。
これらの養成施設には、大学と専門学校の2種類があります。
大学では、専門科目に加えて一般教養科目を幅広く学ぶことができ、より深く学術的な知識を習得できます。
一方、専門学校は、より実践的な技術と知識の習得に特化したカリキュラムが組まれており、早期に臨床現場で活躍したいと考える人に向いています。
どちらの施設を選択しても、解剖学、生理学、運動学などの基礎医学から、それぞれの専門分野に特化した知識や技術を体系的に学び、病院や施設での臨床実習を通じて、実践的なスキルを身につけることができます。
自身の学習スタイルや将来のキャリアプランに合わせて、大学と専門学校のどちらが適しているか検討することが重要です。
柔道整復師と理学療法士のダブルライセンスについて
柔道整復師と理学療法士の資格を両方取得する、いわゆるダブルライセンスはそれぞれの専門性を補完し合い、キャリアの選択肢を大きく広げる可能性があります。
ダブルライセンスのメリット
柔道整復師と理学療法士のダブルライセンスは、キャリアにおいて多くの利点をもたらします。
まず、両方の資格を持つことで、外傷の急性期から機能回復のリハビリテーションまで、患者さんの状態に応じた一貫した治療を提供できるようになります。
これにより、患者さんの早期回復に貢献できるだけでなく、医療現場での対応能力も向上します。
例えば、柔道整復師として外傷の応急処置を行った後、理学療法士としてその後のリハビリテーションを継続して担当できるため、患者さんにとっても安心感が増します。
また、柔道整復師と理学療法士の両方の専門性を活かすことで、就職先の選択肢が広がり、接骨院や整骨院だけでなく、病院やクリニック、介護施設など、より多くの分野で活躍できるようになります。
さらに、自身の専門性を高めることで、他の医療従事者との連携もスムーズになり、より質の高い医療を提供することにもつながるでしょう。
結果として、ダブルライセンスは、自身の市場価値を高め、キャリアアップや収入アップにもつながる可能性を秘めています。
まとめ
柔道整復師は、骨折、脱臼、打撲、捻挫などの急性期の外傷に対し、手術をしない非観血的療法で施術を行います。理学療法士は、病気や怪我、高齢などによって身体機能が低下した人々に対し、運動療法や物理療法を用いて身体機能の回復や維持を支援するリハビリテーションを専門としています。
両者の業務内容や活躍の場、年収、資格取得の難易度には違いがありますが、どちらの職種も患者さんの身体の不調を改善し、社会復帰を支援する重要な役割を担っています。
ご自身の興味や適性、将来のキャリアプランを考慮し、最適な選択をすることが大切です。
柔道整復学科の
イベントのご紹介
オープンキャンパス・イベント
日本医専では実際の授業や校内の雰囲気を体験できるオープンキャンパス・イベントを開催しています。柔道整復師をめざす第一歩として、ぜひご参加ください。









